1.なぜあなたの「28年の知識」は評価されないのか?

私たちは皆、「暗黙知」の牢獄に囚われている
プロジェクトを20年、25年と経験してきた50代SEの頭の中には、「データベースの裏側の挙動」「過去の失敗パターン」「どのベンダーを選ぶべきか」といった、若手には決して真似できない「知識の宝」が眠っています。
しかし、なぜでしょう。私たちは、その知識量に見合った評価や報酬を得られているでしょうか?
多くの現場で、私たちの知識は「あの人は何でも知っているが、何を頼めばいいかわからない」という曖昧な評価に留まり、次第に「伝わらない知識」として組織の隅に埋もれていきます。
前回の記事では、人を動かすための「翻訳力(戦略的コミュニケーション)」について解説しました。
それは、主張を相手の利益に変換するスキルでした。今回のテーマは、その前段階。そもそもあなたの「知識」自体を、確実に相手に渡せる「価値(資産)」に変換する技術です。
長年の経験で培われた私たちの知識は、言語化されずにいると「暗黙知」となり、まるで「牢獄」のように、あなたの頭の中に閉じ込められてしまいます。
この牢獄から知識を解き放ち、組織の「共有知」として流通させる技術こそが、50代SEのキャリアを再加速させる命綱となるのです。
2.スキル2の核:経験を「仕様書」に変える2つの技術
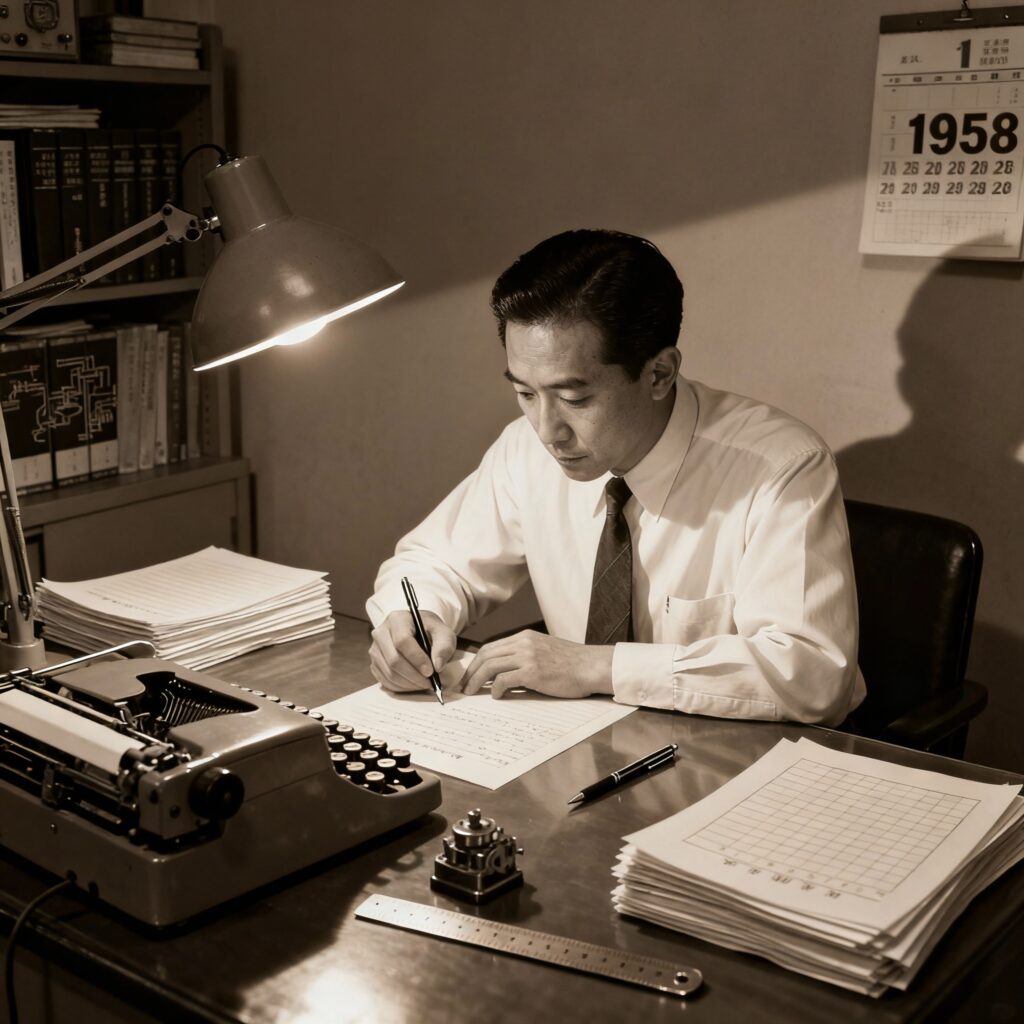
2-1. 技術1:【知識を「型」にする技術】(経験を再利用可能な資産に変える)
経験は「手順書」として残さないと、組織で再利用できない
前述の通り、私たちベテランは、相手の求めた情報1に対して、「運用で起きるリスク8」まで過剰に与えがちです。
これは、私たちの経験が頭の中で「物語」や「教訓」として残っているだけで、誰でも使える「手順書」や「チェックリスト」といった 『型』 になっていないからです。
私の失敗は、その「8の情報」を口頭で伝えたことにありました。その結果、その貴重な知識は「教えた若手個人の暗黙知」となり、組織全体の資産として残ることはありませんでした。
これが、「知識の共有不足」という問題の送り手側としての私の失敗です。
そして、その反省から繋がるのが、受け手側としての私自身の苦い経験です。
私も30代の頃、新しいシステム開発のたびに、先輩が口頭で教えてくれたはずの「コーディングの仕方」「テストでの確認すべきチェック項目」といったコアな知識を、毎回のようにドキュメントのない中からゼロベースで探し直すという非効率を繰り返していました。当時の私は、「これが仕事だ」と思っていました。
しかし、もし先輩があの口頭での指導を「汎用チェックリスト」という『型』にして残してくれていれば、私は2日間の調査工数を、5分の確認作業に短縮できたはずです。
口頭での「 1対1の伝達」を続けた結果、知識は組織で再利用されず、メンバーがそれぞれゼロから探し直すという「非効率な再生産」を招いてしまうのです。
本当に必要なのは、その時々のプロジェクトに特化した詳細なドキュメントではなく、あなたの長年の経験の中から抽出した「汎用性の高いチェックリスト」です。
例えば、「新規システム開発における3つの汎用チェックポイント」として、あなたの経験を以下のように型化できます。
- 【環境構築フェーズ】 「アクセス権限」の設定は、「最小権限の原則」に基づき3回ダブルチェックしたか?
- 【コーディングフェーズ】 **「エラーログの出力仕様」は、「誰でも原因を特定できる粒度」になっているか?
- 【リリースフェーズ】 「ロールバック手順」は、本番環境で10分以内に実行可能なレベルで文書化されているか?
このように、あなたの知恵を「Yes/No」で答えられる「行動」に変換するだけで、知識は組織の資産になります。
2-2.技術2:【「伝わる図」と「結論ファースト」】(アウトプットの型)
ドキュメントの最初1ページ、できれば最初の1行に、**「このドキュメントが示す、最も重要な結論」を必ず明記します。
結論は、「意見」ではなく「事実と行動」でなければなりません。
- 悪い例: 「DB設計について検討した結果を報告します。」(結論なし)
- 良い例: 「結論:来週月曜までにRDBMSをAからBへ移行すべきであり、その理由は3つのコストメリットがあるためです。」
この1行があるだけで、読み手は以降の複雑な図解やデータに目を通す「価値」を感じてくれるようになります。
ドキュメントの「見た目」と「構造」こそが、読まれるか否かを決める
知識を「汎用性の高い型(チェックリストや手順書)」にしたとしても、そのアウトプットの「見た目(図解)」と「構造(結論ファースト)」が悪ければ、結局は読まれずに棚の奥にしまわれてしまいます。
特に50代SEの世代が作成してきたドキュメントは、しばしば「文字が多すぎる説明書」か「技術者しか理解できない複雑な構成図」に偏りがちです。
現代のビジネス環境、特に若手は、読む負担が大きいドキュメントは「開かない」という選択をします。あなたの貴重な経験を資産化するためには、「読み手が3秒で理解できるドキュメントの型」を身につける必要があります。
【伝わる図解】「モノ」ではなく「情報の流れ」を図示せよ
私たちが過去に描いてきた図は、「サーバーとネットワーク機器がどう繋がっているか」という「モノ(物理構成)」を示すものが大半でした。しかし、プロジェクトで本当に必要なのは「判断」であり、判断に必要なのは「情報」です。
【設計者の視点への転換】
システムを設計するプロとして、私たちが提供すべきは、単なる機器配置図ではありません。図示すべきは、「業務フロー」「意思決定のロジック」など、「情報がどこから入って、どう処理され、どこへ向かうか」というビジネスを動かす「仕組み」の流れです。
【私の経験】
私も、運用のリーダーをやっていて、チームメンバーに詳細な物理構成図を渡して「自分で見て判断しろ」と言った結果、復旧に時間がかかった苦い経験があります。どういう観点で見るなどの情報がないもののみを渡して判断させるのは難しいと思いますし、同じベテランであればできることも、若手にそれを求めるのは難しいと把握しておくのが大事だと思います。
3. まとめ:知識を資産化する「ドキュメント・言語化技術」の価値
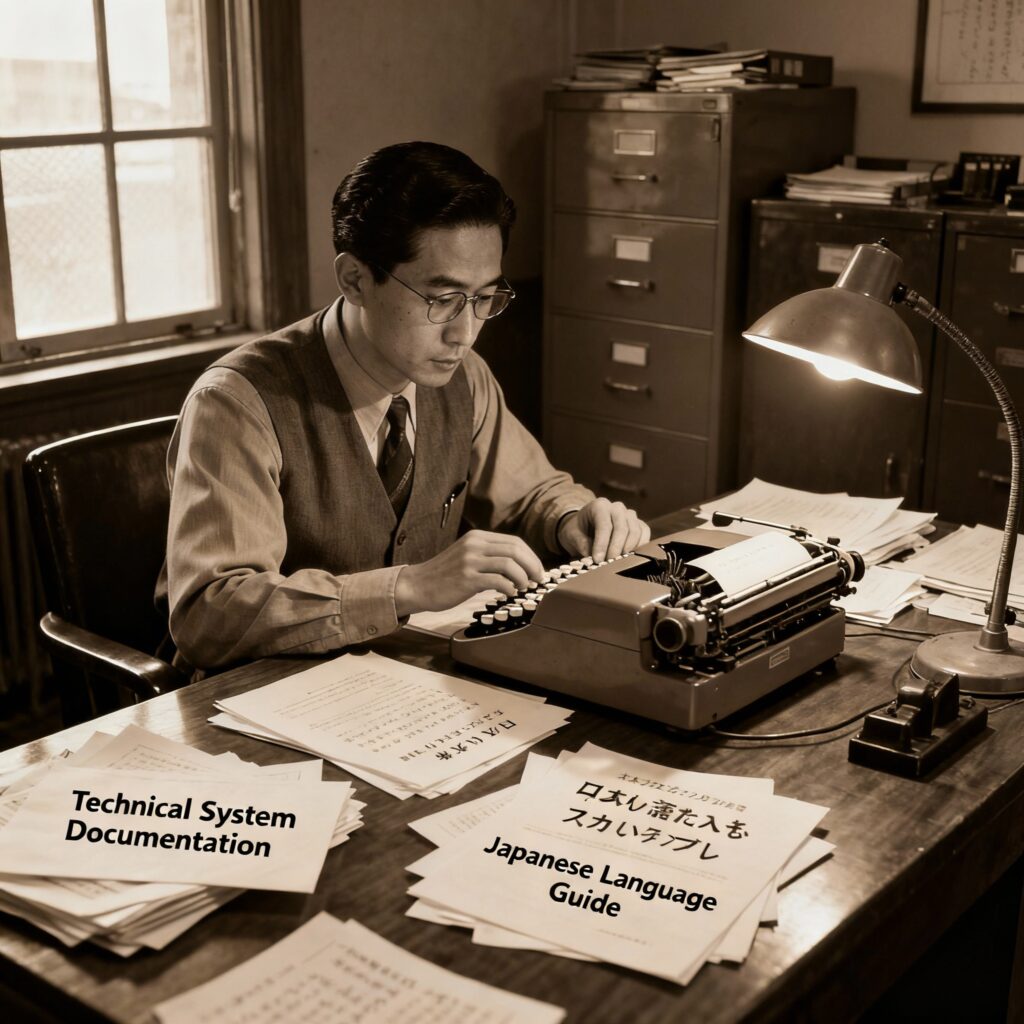
本記事では、50代SEのキャリアを再加速させる非技術的スキル3つのうち、「知識を資産化するドキュメント・言語化技術」について深掘りしました。
あなたの28年の経験は、口頭で伝えた瞬間に「暗黙知の牢獄」に囚われてしまいます。その知識を組織で評価される資産に変えるには、以下の2つの技術が不可欠です。
- 知識の「型化」:
- 経験を「汎用性の高いチェックリストや手順書」として残し、誰でも再利用可能な組織の共有知に変えること。
- アウトプットの構造化:
- ドキュメントを**「モノ(機器配置)ではなく、情報の流れ」**で図解し、結論ファーストを徹底することで、開いてすぐに役立つ高い再利用性を獲得すること。
- 知識を「型」にすることで、あなたは「教える人」から「チームの生産性を向上させる仕組みを作る設計者」**へと進化します。
- 結論ファーストを徹底することで、あなたの提供する情報は「読まれる資料」となり、社内での信頼度(ブランド)を飛躍的に高めます。
次回予告: 50代SEの「停滞」を防ぐ最終スキル
最高のドキュメントを作成し、人を動かすスキルを身につけたとしても、キャリアはこれで完成ではありません。外部環境や技術は常に変化しています。
50代SEにとって最も恐れるべきは、知識の陳腐化と「これで十分だ」という停滞です。過去の成功体験が、あなたの未来を阻む最大の壁となってしまうからです。
最終回の【キャリア3部作】第3弾では、「常に学び続け、自分自身をアップデートする技術」に焦点を当てます。
【非技術的スキル 3】 50代SEの自己成長術:知恵を更新する「傾聴と内省の習慣」
ぜひ次回の記事もご覧ください。


