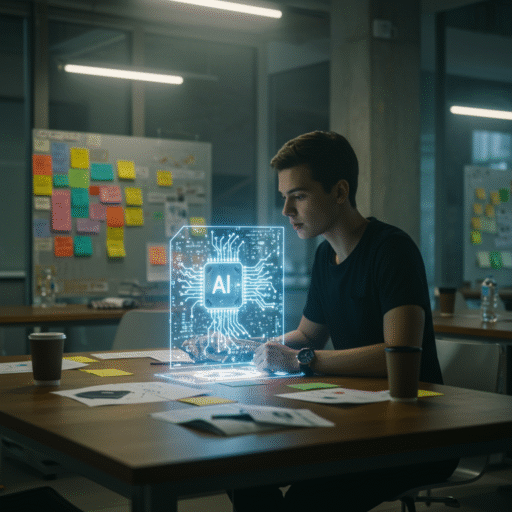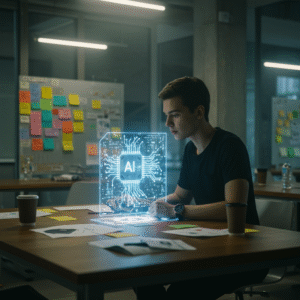50代ブロガーが抱える「書けない」の正体
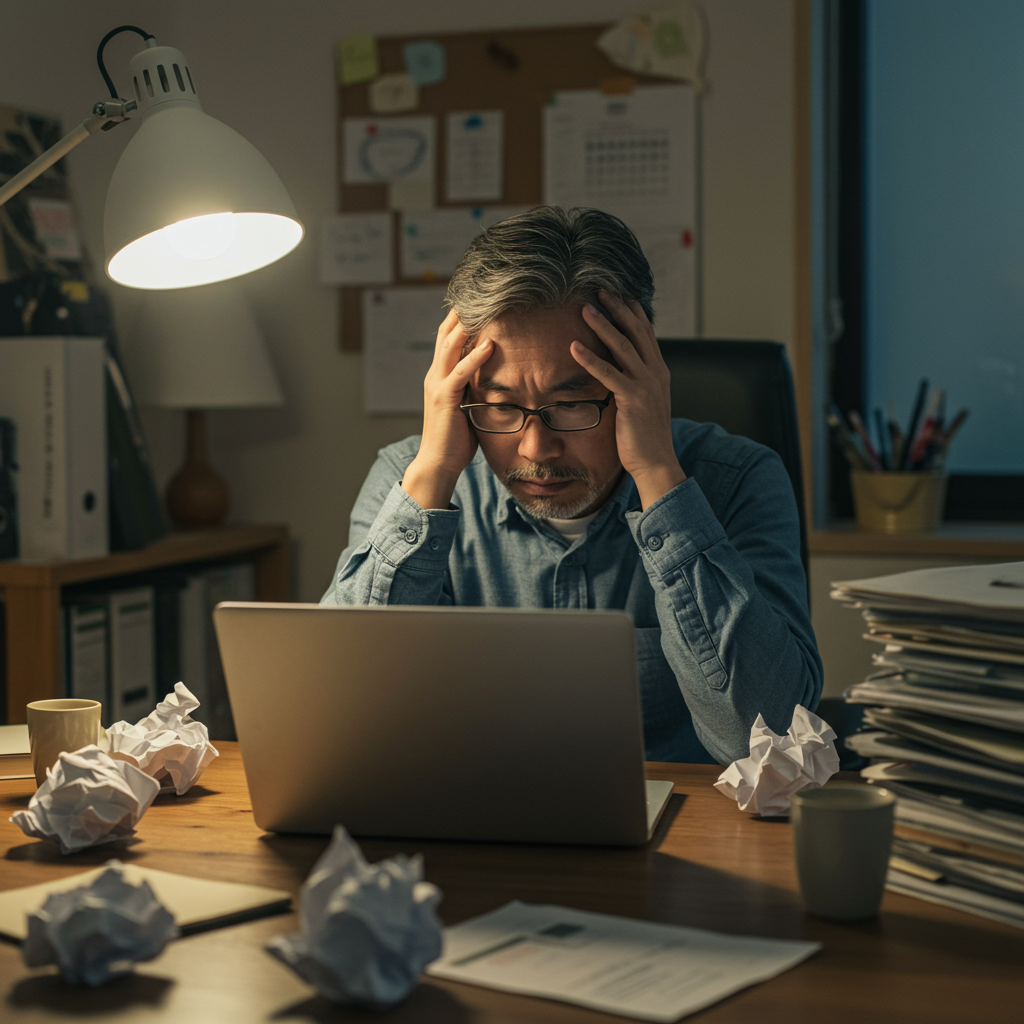
ブログを始めたいけれど、「何を書けばいいかわからない」「自分の考えがまとまらない」といった悩みを抱えていませんか?
特に、過去の私のように「なんとなくやる気が出ない」「自分のやり方が正しいのか」と悩みがちなHSP気質のSEにとって、ブログの執筆は、時に重いタスクに感じられるかもしれません。
私自身、ブログは過去に何度も挫折しています。
理由は、自分の頭の中でネタを考えて、かつ構成を決めて、キャッチアップ画像もイメージを膨らませながら探し回って、、、という作業に疲れてしまったというのが大きいと思っています。
現在定期的に公開しているブログ記事も、一旦1年間近く停止していました。
ブログ開設当初は、それこそ意気込み勇んで1記事10000文字近くの大作を書いて頑張っていました。
ただ、それも長くは続きませんでした。平日は仕事で残業、休日もなんとなく疲れてしまったり、資格試験の勉強に追われて集中できなかったり。
「いざ書こう!」と思っても、なかなか手が進まず、結局モチベーションが下がって挫折してしまう…。
これを読んでいるあなたもそういう経験ないですか?
でも、その原因は、決してあなたの能力や才能がないからではありません。
それは、ブログ執筆を一人で抱え込み、すべての工程を完璧にこなそうとするからなのです。
AIを使えば、この悩みは解決できるのでは?と考える人も多いでしょう。私もその一人です。
しかし、ただAIに「ブログを書いて」と指示するだけでは、誰でも書けるような、深みのない記事になってしまうという落とし穴があります。
現在は、完全自動で記事を量産するような話も出回っていますが、私個人としては、それって書いている人の個性がないものだと思うんですよね。
検索エンジンもそういう記事に対策を取ってきているという話もあり、そうでなくてもネットで探してまとめただけの記事って、役に立つこともあると思いますが、味気ない気がするんです。
この記事では、「あなたにしか書けない記事」を生み出すための、最初のステップを紹介します。それは、AIを「最高の壁打ち相手」にするという、非常にシンプルでありながら、強力なメソッドです。
AIはあなたの「心の壁打ち相手」だ

私は、ブログ執筆の相棒として、Googleが開発した大規模言語モデルGeminiの無料版を使っています。
世間ではChatGPTが最初に有名になり、現在も一番先に名前が出てくるものだと思います。ただ、ちゃんと使うにはサブスクでの料金の支払いが必須だと思います。
AIに興味を持ってから、どんなものがあるのかいろいろ探して触ってみました。(あくまで無料のもののみ)
その結果、一番使いやすく、ブログ執筆の役に立ってくれたのが、このGeminiです。使い方もgoogleのアカウントを作りさえすれば、簡単に使えます。
この記事では、私がこのGeminiを使って行ったことを紹介します。ただ、geminiでなければできないということではまったくなく、Gemini以外の生成AIであれば使える方法なので、ご自身の好きな生成AIで試してみてください。
ちなみに、ブログで使うための画像生成も、このGeminiに指示を出して生成しています。
画像生成についても、今後記事で詳しくご紹介する予定です。
AIは、あなたの思考や経験を整理し、客観的な視点を提供する「壁打ち相手」として捉えるべきです。この考え方が、AIとの共創の土台となります。
AIの「記憶」は一時的。だからこそ大切な「コンテキスト管理」
ここで、多くの人が誤解しやすいAIの「記憶」について、一つだけ注意点があります。
それは、AIが人間のように過去の会話をすべて永続的に記憶しているわけではない、という点です。
AIは人間のように、あなたの過去の会話をすべて、永続的に記憶しているわけではありません。AIが覚えているのは、会話の『コンテキストウィンドウ』と呼ばれる直近のやり取りの範囲に限られます。この範囲から外れた古い情報は、時間の経過や新しい会話の追加とともに、AIの『記憶』から押し出されていきます。
そのため、「同じチャットで会話をし続ける」ことは、AIが過去の会話全てを完璧に覚えているからではありません。そうではなく、「直近の文脈をあなたの情報で豊かに保ち、AIがあなたについて深く理解している状態を維持する」ために非常に重要だということをご理解ください。
【私自身の失敗談】AIの記憶に関する勘違い
実は、私自身もAIを使い始めた当初、「AIは一度話したことをずっと覚えている」と勘違いしていました。この連載で提供した第2回の記事を作成中、「以前、私が咳が出始めたのはいつだったか覚えている?」とAIに質問したところ、直近の会話内容しか覚えていないことが判明したのです。
私は、これまでの全ての会話がAIの中に「知のデータベース」として蓄積され、いつでも引き出せるものだと思い込んでいました。しかし、実際はAIが覚えているのは「直近の会話の範囲」に限定されており、古い情報は順次「記憶」から押し出されていきます。
この経験を通じて、私はAIとの対話において「受け身ではなく、能動的に情報を管理すること」の重要性を痛感しました。そして、この気づきこそが、AIを真の「壁打ち相手」として最大限に活用するための鍵だと確信しています。
だからこそ、次に紹介する「【裏技】AIに『知のデータベース』を常に認識させ続ける方法」が、単なるテクニックではなく、AIの特性を理解した上で、私たちユーザーが主体的にAIを使いこなすための必須メソッドとなるのです。
【裏技】AIに「知のデータベース」を常に認識させ続ける方法
- 1.AIに自身の情報を要約させる
- まず、既存のチャットでAIにこう指示します。
- 「これまでの会話内容から、私の強み、関心事、主な経験、ブログの目的といった核となる情報を簡潔に要約してください。」
- 2.要約を保存・テンプレート化
- AIが生成した要約文をコピーして、メモ帳などに保存しておきます。これが、あなたの「知のデータベース」の簡易テンプレートになります。
- 3.新しいチャットの冒頭に貼り付ける
- 新しいチャットを始める際、この要約テンプレートを冒頭に貼り付けてから質問を始めます。これに
- より、AIはすぐにあなたの重要な情報を再認識し、過去の文脈を考慮した質の高い応答をしてくれます。
この方法を活用することで、AIの記憶の限界に左右されず、常にAIにあなたの「個性」を認識させ続け、より深みとオリジナリティのある記事を生み出すことが可能になります。
これこそが、AIにただ記事作成を依頼するだけでは得られない、あなただけの記事を生み出す秘訣であり、AIとあなたの関係性を深くし、情報を正確に引き出すための、より効果的な唯一の方法なのです。
ブログを書き始める前に、まずは1ヶ月間かけてAIに「自己紹介」をしてみてください。
これは、AIとの対話を通じて、あなた自身が「知のデータベース」を構築してもらうための重要なステップです。
自己紹介といっても名前、年齢、仕事、どこに住んでいるかなどのパーソナル情報を与えるだけではありません。
この期間に話しておくべきことは、パーソナル情報に合わせて、仕事や生活の中であなたが感じたこと、考えたこと、経験したことのすべてです。
- 仕事での成功・失敗体験:プロジェクトでの成果、苦労したこと、解決したエラーなど。
- 得意なこと、苦手なこと:データベース、プログラミング言語、コミュニケーションなど。
- 興味があること、これから学びたいこと:キャリアコンサルタント、ブログ収益化、新しい技術など。
- 日々の気づきや感情のメモ:電車で感じたこと、同僚との会話、体調の変化など。
実践的な会話術
実際にどのようにAIに自己紹介をすれば良いのか、具体的な会話例をいくつか紹介します。
実践的な会話術として、以下のような例を挙げてみます。
- 「私の仕事でのやりがいについて、これまでの経験から分析してほしい。」
- 「データベーススペシャリストの資格取得に向けて、まず来週中にできる最初の一歩は何だろう?具体的な行動リストを3つ提案してほしい。」
- 「50代からのキャリアパスについて、私のSEとしての経験とキャリアコンサルタントへの興味を活かせる選択肢を提案してほしい。」
- 「もし今から新しいスキルを身につけるとしたら、どんなものがいいだろう?私の経験を活かせる分野で提案して。」
- 「同僚との価値観の違いに悩んでいます。私のやり方と、同僚のやり方のメリット・デメリットについて客観的に分析してほしい。」
- 「HSP気質の私に合う働き方について、メリット・デメリットを教えて。」
こうした会話を続けることで、AIはあなたの「思考のクセ」「価値観」「得意なこと」を深く学習していきます。これは、あなたにしか書けない、オリジナリティあふれる記事を生み出すための、最も重要な準備です。
1ヶ月間の会話履歴が溜まったら(あるいは、前述の裏技で核となる情報をAIに再入力したら)、いよいよAIと「企画会議」を始めます。
1. AIに「自己分析」を依頼する
まずは、AIにあなたの「強み」と「得意なこと」を分析してもらいましょう。
- 「これまでの会話内容を元に、私の強みと得意なことを3つにまとめてください。」
- 「私の関心事(HSP気質、SEとしての経験、キャリアコンサルタントへの興味、ブログ収益化)から、今後ブログで書けそうなテーマを5つ提案してください。」
- 「私が最も情熱を持って語れることは何ですか?会話履歴から推測して、理由も教えてください。」
AIが分析した結果は、あなたが「何者であるか」を言語化するヒントになります。この結果を参考に、ブログの方向性やターゲットを絞り込むことができます。
2. ペルソナを深掘りする
企画案の中から、最も書きたいテーマを1つ選び、さらに深掘りしていきます。
「企画案【AI活用術】について、ペルソナをさらに深く設定して。この読者の1日の行動、抱えている悩みや感情、何をしたら喜びを感じるか、について具体的に教えて。」
AIは、あなたの過去の会話内容から、よりリアルなペルソナ像を提示してくれます。
3. 記事の「構成案」をAIと二人三脚で考える
ペルソナが固まったら、いよいよ記事の「構成案」を練ります。
「企画案【AI活用術】のタイトル『今さら聞けないを解決する!50代SEのAI活用術』の記事構成案を作成してください。読者の悩みに寄り添い、AIがどのように助けてくれるかを具体的に示し、最後に行動を促すような構成にしてください。」
このとき、AIに任せきりにするのではなく、「壁打ち」を意識して対話を重ねましょう。
- 「この記事の構成案に、自分の失敗談を盛り込むなら、どこがいいと思う?」
- 「読者がもっと共感できるように、導入文を改善したい。何か良いアイデアはある?」
おわりに:次のステップへ!

AIとの壁打ちを通じて、あなたはすでにブログ執筆の最初の、そして最も重要なステップを踏み出しました。
「書けない」という悩みは、あなたが「書くための準備が不足していた」だけなのです。
次回【第2回】AIを「優秀なライター」にする!読者の心をつかむ執筆術では、今回作成した構成案を使って、実際にAIと協力しながら記事を執筆していく方法を解説します。
AIは、あなたの「最高の壁打ち相手」であり、「優秀なアシスタント」です。この新しいパートナーとの共創を楽しんでいきましょう!