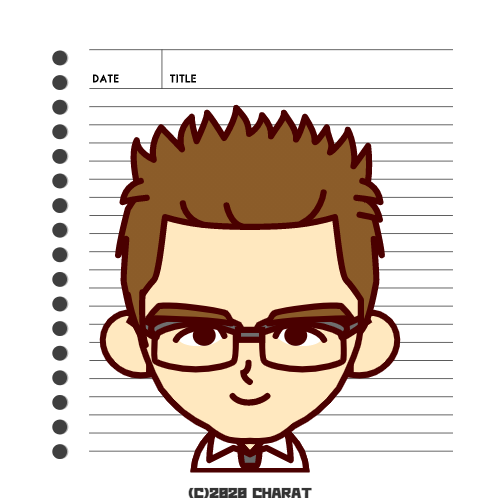※この記事は個人の体験と知見に基づいています。
医療的な助言ではないこと、また成果を保証するものではありません。
免責事項の全文はこちらをご参照ください。
時計はすでに22時を回っている。周囲の明かりが消え、静まり返ったオフィスで、私は一人、メンバーが作成した設計書の一行一行を食い入るように見つめている。
「ここ、異常系の考慮が漏れていないか?」 「このパラメータ、運用フェーズで変更したくなったらどうするんだ?」
次々と浮かぶ懸念をメモに書き出しながら、ふと深い溜息が出る。
本来、PM(プロジェクトマネージャー)の役割は、設計・開発・テストの大半をメンバーに任せ、自分は大局的な管理に徹することだ。しかし、現場に立つとそうはいかない。
「本当にこの設計で大丈夫か?」「テストケースに漏れはないか?」という不安が、長年の経験からくる「検知センサー」を激しく刺激するからだ。
1.現場のジレンマ:なぜ「手」を出してしまうのか

特に頭を悩ませるのは、メンバーとの「運用のアンテナ」の差である。
設計レビューの際、大枠の内容は理解していると思われるメンバーでも、実態は「機能がなんとなく動くもの」を作ることに終始し、その先の運用まで考えられていないことを知った時には、深い残念さを感じることが多い。
もちろん、メンバーも苦労している。長年の経験を持たない彼らにとって、運用を見据えた設計ができないのは、ある種仕方のないことかもしれない。こうしたアンテナは、その立場になって修羅場を経験しない限り、言葉で教えてもなかなか身につかないものだからだ。
そのため、実際の事象(トラブルや課題)を通して教えていくことになるが、定着するまでには時間がかかり、一回で伝えきれるものではない。しかし、誰かがそれを理解し、伝え、品質を担保しなければならないのも事実である。その「見えてしまう頭」がある私は、どうしても手を出してしまう。
気づけば、細部までチェックし、時には自分で修正案を作り、説明し、運用まで持っていく。その結果、システムに大きな問題は発生せず、顧客からの信頼も保たれる。プロジェクトは表面上、平穏に進んでいく。
2.「成功体験」という名の呪縛

なぜ、私たちはこの「身を削るスタイル」を卒業できないのか。それは、このやり方で「品質を守り抜いてきた」という自負があるからだ。
実際に今の現場でも、私はバッチを1本一人で設計からテスト、リリースまで完結させた。
現在もそのプログラムは無障害で稼働し続けている。この「自分でやれば確実だ」という実績があるからこそ、全部の中身を確認しないと、リリース後が怖くてたまらなくなるのだ。
一番怖いのは、リリース後に障害が発生し、その原因が担当者の開発ミスだった時だ。
緊急対応のために夜中であっても呼び出される。そして、その問い合わせ先は基本、私だ。
対応した後も、顧客への謝罪、一次対応、その後の恒久対応に追われる。その凄惨な地獄を何度も見てきているからこそ、責任がすべて自分に返ってくる恐怖を、自分の稼働を上げることで埋めてしまう。
しかし、ここで冷静に脳科学的な視点を入れてみたい。私たちが「安心」を買うために現場の細部をチェックしている時、脳のメインメモリは完全に「現場作業」に占拠されている。本来すべきPM業務は後回しになり、早朝や定時後の静かな時間に、削られた気力でようやく着手する。
この状態では、プロジェクトの数歩先にあるリスクを察知したり、組織を改善したりするための「高度な判断力」は機能しなくなっている。いくらマルチタスクに慣れた脳でも、いつかオーバーヒートを起こすのは火を見るより明らかだ。
世間一般にも言われていることだが、実務を兼務し続けるPMがいるプロジェクトは、いつか必ず破綻する。それは、PM個人の限界が、プロジェクトの限界になってしまうからだ。
3.「脳のマルチタスク限界」と「不信感のビット」を科学する

なぜ、これほどまでに脳が疲弊し、フリーズしてしまうのか。それは単に「仕事量が多い」からではない。
心理学的な観点から見れば、私の脳内では「心理的境界線」が消失し、メンバーが担うべきタスクの責任までもが、すべて自分の領域に流れ込んでいる状態だ。
メンバーの設計に不安を感じ、細部をチェックし始めるとき、私の脳内では一つのフラグが立つ。
私はこれを「不信感のビット」と呼んでいる。「本当に大丈夫か?」という疑念がビットとして立つと、そのタスクは脳の中で「完了」として処理されず、常にバックグラウンドで動き続ける常駐プログラムのようになる。
人間が一度に扱えるワーキングメモリには限界がある。PMとしての意思決定、顧客との調整、予算管理。
これだけでもメモリは一杯なのに、そこに「メンバーが書いた全プログラムのロジック把握」という巨大なデータが居座れば、脳が4つに分割されるような感覚に陥るのは当然の帰結だ。
さらに、最近学んでいる心理学の視点で見れば、これは「期待の投影」という側面もある。
「自分なら運用まで考える」「自分ならこう作る」という自分の中の理想の基準をメンバーに投影し、それが満たされないことに落胆し、自分で埋めようとする。しかし、前述した通り、その「アンテナ」は立場と経験を経て初めて育つものだ。
若手に「最初から自分と同じアンテナを持て」と期待することは、実は無理な要求をしていることにもなりかねない。
教える側が「今は持っていなくて当然」と境界線を明確に引き、教育を「事象が起きた時の対話」に絞る。そう決断しない限り、私の脳のビットが下がることはなく、メモリは漏れ出し(リークし)続けてしまうのだ。
4.「任せる」ことは「品質を下げる」ことではない

「自分が動かないと品質が落ちる」という恐怖は、プロとして当然の感情だ。しかし、一歩引いて考えてみると、ベテランPMが現場の細部に没入している状態は、プロジェクトにとって別の「巨大なリスク」を生んでいる。
それは、「PMの脳が、全体を俯瞰する能力を失う」というリスクだ。
現場の作業で脳が100%占有されている間、プロジェクトの数ヶ月先に潜む契約上のリスクや、他部署との調整、組織的な予兆といった「PMにしか見えないはずの景色」が、完全に死角に入ってしまう。
私たちが目指すべきは、自分が動いて100点を取ることではなく、たとえメンバーが60点の成果物を出してきたとしても、それを組織として80点に押し上げる「仕組み」や「チェックポイント」を作ること。
自分が手を動かしている間、オーケストラに指揮者は不在となる。
指揮者のいない演奏は、個々のパートがどれだけ優秀でも、全体としての調和を欠き、いつか破綻する。
私がすべきは、メンバーの代わりに楽器を弾くことではなく、彼らが迷わず演奏できる「楽譜(プロセス)」を整え、全体のテンポを調整することだ。脳のリソースを作業ではなく、その「構造の構築」にシフトさせることこそが、ベテランPMが目指すべき真の品質担保ではないだろうか。
5.まとめ:プロとしての「自分への許可」

人員不足、過酷な納期、体制の不備。これらを自分の個人の負荷で埋めるのは、日本的な「美徳」かもしれない。しかし、その美徳の果てにあるのが「脳のフリーズ」や「心身の摩耗」だとしたら、それはもはや持続可能なプロの仕事とは言えない。
ベテランが現場の穴を埋め続ける限り、組織の欠陥は隠され続け、本当の意味での人員改善や仕組みの導入は行われない。私が自分の限界を超えて頑張ることが、結果として組織の成長を止めているという側面もあるのだ。
今の私に必要なのは、自分をさらに追い込む努力ではなく、「自分の脳の余白を死守する」という、自分自身への許可を出すことだ。
ベテランが現場の穴を埋め続ける限り、組織の欠陥は隠され続け、本当の意味での人員改善や仕組みの導入は行われない。時には「あえて現場の穴を自分の負荷で埋めない」という勇気が必要なこともある。
余裕を持った脳で、プロジェクトの行く末を正しく見定めること。 時には「あえて現場の穴を自分の負荷で埋めない」という勇気を持ち、組織としての課題を浮き彫りにすること。 それが、30年のキャリアを経て、数億円規模を動かすPMに求められる、本当の意味での責任の取り方であり、新しいプロ意識の形なのだ。
同じように、マルチタスクの限界の中で「自分がやるしかない」と唇を噛み締めているベテランPMの皆さんは多いはずだ。
だが、あえて伝えたい。私たちの価値は、現場の作業を完遂することだけにあるのではない。余裕を持った脳で、プロジェクトの行く末を正しく見定めることこそが、本来の役割だ。
そのために、時には「動かない自分」を許す。それは怠慢ではなく、プロとしての重要な決断なのだ。
この記事を書いている今は、ちょうど年末。 年が明けて初日の出勤時、私は少しだけ「任せる」勇気を持ってデスクに向かおうと思う。それは、私自身にとっても、そしてプロジェクトにとっても、新しい一歩になるはずだ。
その時、私の脳には、そしてこの記事を読んでくださった皆さんの前には、今まで見えていなかった「新しいプロジェクトの景色」が広がっているに違いない。