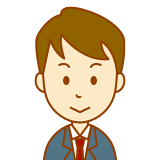
HSP気質なんだけど、どういうキャリアパスが有利とかある?
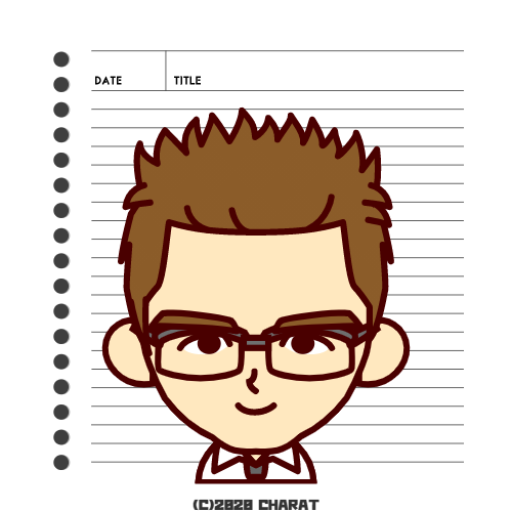
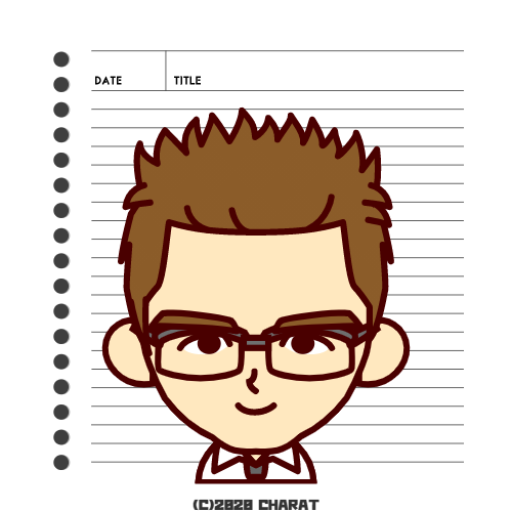
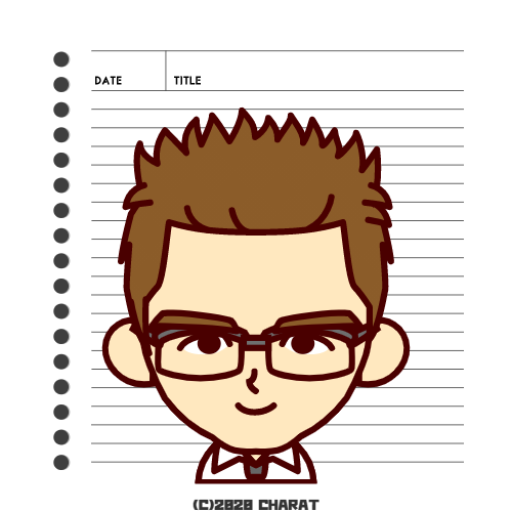
そんな疑問にHSP気質のでシステムエンジニアを20年以上やっている私の視点でお答えします。
HSP気質の人がシステムエンジニアになるにあたってのおススメのキャリアパスを紹介したいと思います。
一般的に言われている話と、現在私の従事している仕事から考えたものとの2つで提示したいと思います。
一般的な話については、私が20数年仕事をしてきた感想を含め書きたいと思います。
一般的に言われているキャリアパスとその感想
まずは一般的に言われているものから紹介します。
フリーランスエンジニア


フリーランスエンジニアは、サラリーマンより自分のスケジュールを自由に管理できるため、ストレスを最小限に抑えることができます。また、自分の興味や得意分野に合わせてプロジェクトを選ぶことができるため、やりがいも感じやすいと言われています。
実際、うまくプロジェクトを選ぶことでHSP気質につらい現場を避けることができると思います。
ただ、会社という隠れ蓑を無くして自分を売り込んでいかなければならないので、より個人でのスキルアップが必要になり、自分のできることを明確に把握しておく必要があります。
加えて、スケジュールの厳しいプロジェクトや、出社必須、どこかの会社の社員のような動きをしなければならないようなところは、スケジュールを自由に管理ということは難しいのではないかと思います。
うまく自分に合ったプロジェクトに入れれば、自分をうまく生かして仕事ができるはずです。
研究者またはアカデミアン


HSP気質のシステムエンジニアは洞察力や直感力に優れているため、研究者またはアカデミアンとして新しいアイデアや革新的な解決策を考えるのに適しています。研究や学問に取り組むことで、個別のプロジェクトに集中しやすく、自分のペースで進めることができると言われています。
これについては、私はそのキャリアは難しいので、どうという意見はいけないのですが、1つのことに集中して取り組むのは得意なので、なれれば取れもいい職、キャリアではないでしょうか。
UX(ユーザーエクスペリエンス)デザイナー


UXデザイナーとは製品やサービスのUXを設計する職種です。最近の職種ですね。
UXとは製品やサービスに触れたときにユーザーが得られる体験のことを指すものです。
ユーザーが迷わずにページにアクセスしたり、機能などをストレスなく利用できるように設計するような仕事になりますね。
HSP気質の人はユーザーの感覚や感情に敏感であり、ユーザーエクスペリエンスデザインにおいて大きなアドバンテージを持ちます。システムやアプリケーションの使いやすさや快適さを追求する仕事であり、HSP気質のシステムエンジニアには適していると言われています。
ユーザーの感覚、感情をしっかり見て仕事に活かせるようにする訓練などは必要かと思いますが、キャリアの一つとして考えておくのはありだと思います。
HSP気質の私のキャリアで考えるおススメキャリアパス
ここからはサラリーマンとしてシステムエンジニアを20数年行っている私の観点で、おススメなものをご紹介していこうと思います。
上記ではキャリアパスというより、その職種のようなものを書きましたが。ここでは年代別も含めた、このようなキャリアを積んでいければということを書きたいと思います。
ここで挙げるものは1例ではあるので、それが正解というものではありません。自分の考えるキャリアと照らし合わせてみていただければと思います。
まず、システムエンジニアの職種は多岐に渡るものの、一部を除いて基本的には以下の流れを取ると思います。
- 顧客からの要望を聞いてまとめる要件定義
- 要件定義書を基にシステムを設計する外部設計
- 外部設計書を基に作成する内部設計書
- 内部設計書を基にプログラミング
- 作成したプログラムの単体テスト
- 単体テストが終わったモジュールを繋げてテストをする結合テスト
- 外部システムを含めてテストをする総合テスト(いろいろな種類がありますが割愛)
- システムをリリースした後の運用・保守業務
この流れをどのようにキャリアを積んでいくのかをお話ししようと思います。
若手時代のキャリアでおススメできるもの
会社に入りたてから数年間のキャリアについて書いていこうと思います。
個人的な意見になるのですが、会社に入った際、プログラミングは行った方がいいと思います。
会社によっては、その開発工程を雇っている会社に丸投げし、社員は管理や調整だけというスタイルで仕事を進めるところも割とあります。
ただ、最初からそのスタイルで仕事を始めてしまうと、後に苦労することになると思います。
なぜならプログラミングを自分で経験することなく、その後の設計などを実施していくと、よくわからないままになり、より良いものが作れないと思うからです。
すくなくともプログラミングを最初にできる会社に入って勉強しておく必要があると思います。
その中でHSP気質の人は、1つのことに集中することが得意なので、プログラミング作業に向いています。
そこからの単体テストも洞察力や直感力に優れていることから、基本を押さえることができれば適切に対応していくことができます。
この点をしっかり学んでプログラミングスキルをつけておくことをおススメします。
この先、このスキルを使ってフリーランスエンジニアになる道も開けると思います。
上記の通り、管理、調整だけやっていたというと、フリーランスエンジニアでやっていくにはかなり厳しい状況になります。
その辺りを考慮して、会社選びをすることも大事です。面接時にその辺りを聞くのもいいと思います。
中堅エンジニアのキャリアでおススメできるもの
プログラミング、単体テストなどをしっかり実施した後、詳細設計や基本設計、場合によっては要件定義フェーズの作業を行っていくことになります。
プログラミング、単体テストの仕方がしっかり身についていると、どういうプログラムを組むはを詳細設計書を見て実施していたはずなので、詳細設計自体は書き方を理解できれば、問題なく実施できると思います。
それ以上の上流工程の作業については、慣れないこともあって不安になることも多いでしょう。
その辺りしっかり先輩社員が教えてくれたり、研修を受けさせてくれれば問題がないのですが、そうではなく年代的にできるでしょ?的に丸投げしてくる場合があります。
そうなってしまうと、いろんなことを深く考えすぎてしまうHSP気質にとっては、ただただつらい作業になってしまう可能性があります。
その点を気をつけて、できないものはできないと上司や周りに宣言しましょう!
できないものをできるように振舞って、後で問題が起きる方が問題が大きくなります。
大きくなった問題は、HSP気質の人に取って、自分を責め過ぎる要因になってしまいます。それが過度になるとメンタル不調になる可能性を上げてしまいます。
なので、わからないことはわからない、わかることはこの部分というのをはっきりさせておくことが大事です。
その上での設計作業は、ものごとを深く考えることができるHSP気質にとって、得意になることができる作業ではあります。
いろいろなものを見て、深く考えてしまい過ぎて不安になってしまうと苦手意識がついてしまうこともあるので、その点は注意ですが、順序良く覚えていくことで問題なく実施できると思います。
加えて、この年代になってくると、チームのサブリーダー、もしくはチームリーダーをすることになるかもしれません。
ここにもHSP気質であることのメリットがあるので、最初不安かもしれませんが、積極的に受けていきましょう!
自分の作業をこなすだけの作業から、他人の作業状況を見ていくようにステップアップしていくわけですが、HSP気質を活かせるポイントがあります。
HSP気質の人は他人の変化に気づきやすいいので、意識すると落ち込んでいる人や、困っている人に気づけると思います。
その人に対して適切に対処することで仕事を円滑に進めることができます。
HSP気質の使いどころです。
ここで気をつけないといけない点を列挙しますので、気をつけていただければと思います。
- 相手のミスを指摘すると気を悪くするかもと思ってしまう。
- 周りのフォローばかりで自分の作業が進まない(パンクする)
- 人に指示する(特に年上)のに苦手意識があり、自分で作業してしまう
- いろいろ頼まれた時に断れない
それぞれ簡単に説明します。
相手のミスを指摘すると気を悪くするかもと思ってしまう。
せっかく相手がミスした部分に気づけても、これを恐れて言えないのがHSP気質。
言った先を想像して言えなくなってしまうのですよね。
そんな時、ミスを指摘するという意識ではなくて、確認するようなセリフに変えてみるのがおススメです。罪悪感を減らすことができます。それで慣れていくと、明確なミスなどを指摘できるようになっていきます。
周りのフォローばかりで自分の作業が進まない(パンクする)
他人が困っていることに気づいて、話かけるなどはとても大切なことではあるのですが、それで相手の作業を引き取ってしまうことが多々あります。
これは全てが悪いことではないのですが、やり過ぎてしまうと自分がパンクしてしまいます。
思考的に先読みし過ぎて、相手の作業の先まで読んで自分で動こうとしてしまうことも原因になります。
なので、意識して自分で作業しないように、声掛けくらいにとどめて、それ以上踏み込まないようにすることが大事です。HSP気質の人は境界線が曖昧になりがちなので、その点をしっかり意識しましょう!
人に指示する(特に年上)のに苦手意識があり、自分で作業してしまう
これ、リーダーになりたてで慣れていないときなどに特に起きてしまうことかと思います。
年上の人などには特に自分に自信がないHSP気質の人は言いづらいと思います。
指示ということを気を言過ぎずにお願いするといったスタンスで、少し気を楽にすることを意識するのがいいと思います。
いろいろ頼まれた時に断れない
リーダーとして作業をしている中で、メンバーの作業だけではなく、上司や顧客から作業をお願いされることも増えていきます。
あまりに断らないと、なんでも言えばやってくれる人になってしまいます。私も過去、断らずにやり続けて、悲惨な目にあいました。
断ること自体が怖くなってしまい、なんでもかんでも受けないといけないという思考になったことすらありました。
そうなってしまった場合、忙しくタスクが詰まっている場合、自分の今の状況を伝えてみましょう。
その上でも仕事を振ってくる人がいれば、それは何も考えていない酷い人かもしれません。
そんなことは多くないと思うので、勇気をもって伝えてみてください。なんでも受けなければいけない状況は変わっていくと思います。
このようなことに気をつけることで、HSP気質の特性を生かして仕事ができると思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
HSP気質はシステムエンジニアには向かないということが言われていますが、まったくそんなことはなく、仕事を選べば活躍できる場所はたくさんあると思います。
もちろん、以下の記事で書いたように向いていない部分も多々存在しますが、それを自覚して意識すれば対応可能です。
これを読んでいただいている方の中で、HSP気質であるが故にシステムエンジニアの仕事が向いていないとか、現在進行形で悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方も一緒に頑張ってみませんか?
何か不明点や確認したいことなどあれば、問い合わせフォームからお願いします。
ここまでお読みいただきありがとうございました。少しでもHSP気質の方の役に立てますように。


