シリーズ:データベーススペシャリスト試験、私の失敗談から学ぶ!挫折からの合格戦略
はじめに:努力が報われなかった真の理由「3つの壁」

前回の記事では、私がどれだけ頑張ってもデータベーススペシャリスト試験に合格できなかった理由が、単なる「勉強時間の不足」や「知識不足」ではなく、「量にこだわりすぎた勉強法」と、その裏にあった「傷つきの回避」という心理的な壁にあったことをお話ししました。
そして、それらの根本原因が、具体的な「3つの壁」として私の前に立ちはだかっていたことを予告しました。
今回は、その「3つの壁」の正体を一つずつ具体的に掘り下げていきます。私が実際にどのようにその壁に直面し、そしてどのように乗り越えようとしているのか、具体的なアプローチとともにお伝えします。
これらの壁は、私同様に資格試験に悩んでいる方の参考になるものだと思って公開します。
壁1:知識を「使う」練習の欠如 — 「わかる」と「できる」の深い溝

あなたは、問題文を読んでいるはずなのに、なぜか設問の意図が見えてこない…そんな経験はありませんか?
分厚い参考書を読み込んだはずなのに、なぜか記述問題になると手が止まる。SQLが書けない。そう感じていませんか?
それが今回紹介する壁の1つ目の中心です!
壁の正体
この壁は、私が最も陥っていた「インプット過多」の学習法によって生み出されました。
参考書を読み込み、studyingの講義動画を見て「なるほど、分かった!」と頭では理解したつもりになるのですが、実際に午後問題を解こうとすると、知識が「使える」状態になっていないため、手も足も出ない。これが「わかる」と「できる」の間に横たわる深い溝です。
午前問題は、問題自体を解答と共に覚えることで6割の合格ラインを超えることができるため、このやり方で全部いいと思っていました。これが大きな失敗でした。
具体的な例として、「ER図の概念は理解しているのに、問題文から自分でER図を描けない」「SQLの構文は知っているのに、業務要件に合った複雑なSQLを書けない」といったものになります。
これでは午後の問題に太刀打ちできるわけないですよね。
なぜこの壁ができたのか(自己分析)
この壁を作り出したのも当然私なのですが、その要因を分析すると以下になると思っています。
「インプットの安心感」
網羅的な知識を頭に入れることだけに集中し、それが「勉強した」という満足感に繋がっていました。
これは結局無駄に時間をかけるだけで、やった感を出していただけでした。過去、学生時代にも同様の勉強法で実施していたのを思い出しました。これで大学受験も1回失敗したのも頷けます。
「アウトプットの負荷回避」
知識を「使う」ためのアウトプットは脳に高い負荷がかかるため、無意識に避けていました。
インプットした後、午後問題でしっかりアウトプットしないといけないのですが、この作業が結局つらいのいでやらずになんとかしようと(無意識に)していたのだと思っています。
よくよく考えると資格試験に受かるためには、これを乗り越えないといけないのですが、苦手なんですよね、結局。
この壁を乗り越えるアプローチ
「ゼロから再現」を徹底する
解説を読み、理解したと思ったら、必ずテキストを閉じ、何も見ずに自分でER図やSQL、記述解答を書き出してみる。
「なぜこうなるのか?」「どうやってこれに至ったのか?」と自問自答しながら、思考プロセスを言語化する練習をする。
この2つを実施することは大事ということに、勉強しながら、AIに相談しながらたどり着いた結果でした。
当たり前でしょ?って思うかもしれません。でも、私の凝り固まった頭で、かつやりたくないという無意識もあったと思うのですが、全然気づかず、手を出さずという状態で過ごしてきました。
結果、前回の記事で書いた通り、たくさんの不合格の山を気づいたんだと思っています。
今、これを少しずつ実践して、理解が進んで来ていると実感しています。
「パターン集」を「再現のためのレシピ集」に
単なる知識のまとめではなく、「この問題文の表現が出てきたら、こう思考して、こうアウトプットする」という思考のプロセスをまとめることをしました。
データベーススペシャリストに限らず、高度情報処理試験の午後問題は、出題パターンがあり、文章の読解が必須です。
この2点を意識して、パターン集をまとめて、問題と照らし合わせて分析をしました。
これを進めることで、苦手な読解も以前よりやりやすくなり、もしかしたら行けるかも?という、今までやっぱり無理かも?という思考から脱却する兆しが見える経験ができました。
もし共感いただけたら、あなたもレシピ集を作ってみてください!結果が変わると思います!!
壁2:論理的思考の練習不足 — 問題文の意図を正確に読み解く力
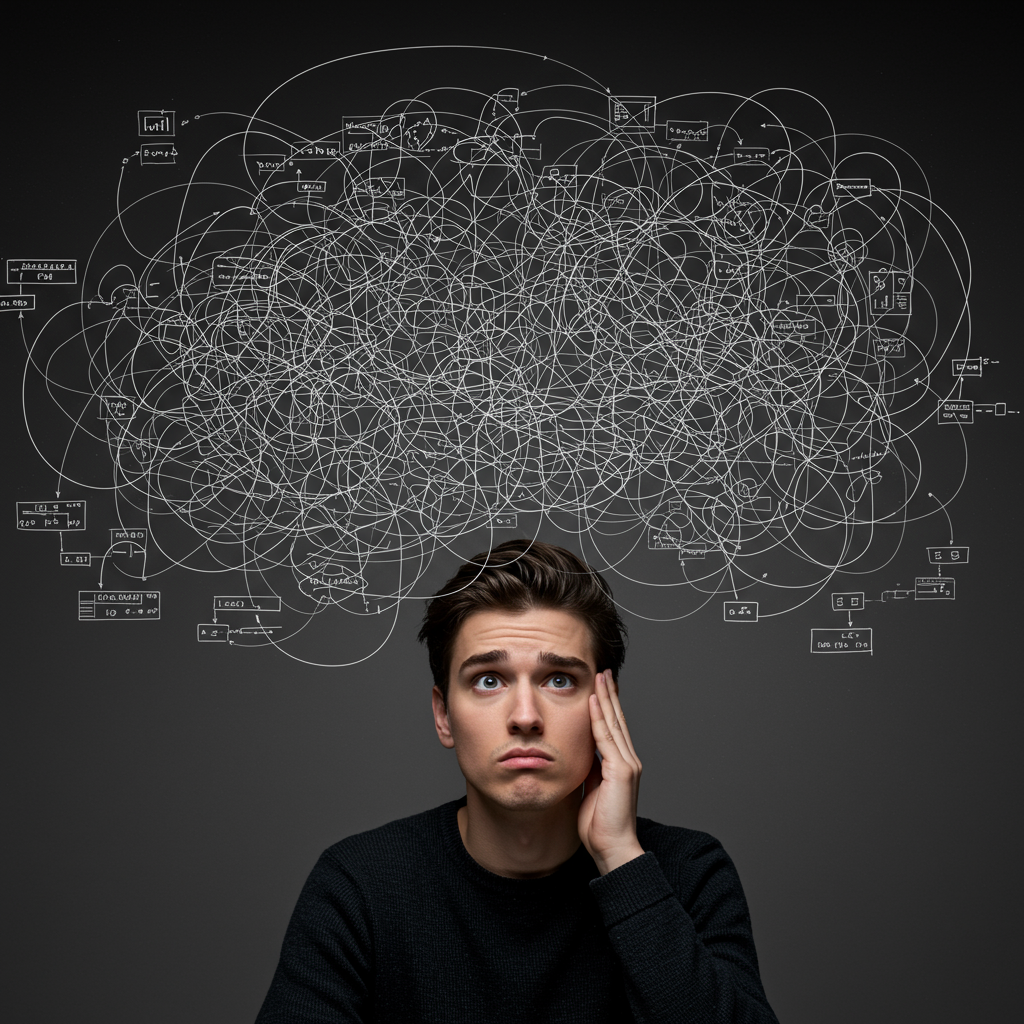
壁の正体
データベーススペシャリスト試験の午後問題は、単なる知識問題ではありません。
長文の問題文から、隠された業務要件、制約条件、矛盾点などを正確に読み解き、論理的に整理する高度な思考力が求められます。
私の場合は、問題文を「なんとなく」読んでしまい、表面的な情報しか捉えられていなかったため、出題者の意図を正確に理解できていませんでした。
具体的な例として、「現行システムの問題点から、変更後の設計にどう繋がるかが見えない」「複雑な業務フローをデータベースの構造に落とし込めない」といったことが挙げられます。
なぜこの壁ができたのか(自己分析)
この壁ができた理由を自己分析してみたところ、以下の2点が挙げられました。
「深読みの欠如」
問題文の情報を鵜呑みにし、行間を読む、裏に隠された意図を推察する練習が足りませんでした。
ただただ問題文を読み、設問に記載のある文字からピンポイントにその文字があるところのまわりだけ読んで解答をなんとなく組み立てるということをしていました。
このことが結果的に私が解答したものと、模範解答とのギャップになり、結果間違う、もしくは薄~い、曖昧な解答になって、答え合わせをした時にしっくりこない状態になってました。
しかも、それを深めていないで、次の問題に取り組んでいたので、わからないまま、わかったつもりで終わっていたのが現実でした。
「情報整理の不得手」
これは、複雑な情報を分解し、構造化して考える習慣がなかったことが原因で苦手になってしまったということです。
長文の最初に方と後の方に書いてある内容の紐づけなど、意識して読んだことがなかったこともあり、整合性が合っていない解答をし続けていました。
そういう読み方、解答の作り方を習慣的に実施できている人に取っては、当たり前のことなのかもしれません。
でも私にはそれがとても難しく、だんだん午後の長文を読むこと自体が嫌になっていきました。
壁1のアウトプットの負荷回避もこの辺りから発生していたような気がします。
この壁を乗り越えるアプローチ

「問題文の徹底的な分解と可視化」
今まではただ過去問を解いて、模範解答と見比べて合っているかどうかを行うところまでで留まって、それでこういう解答になるのかと、なんとなく納得(わかったつもり)で終わらせて、試験に望んでいました。
それでは結局、本当にわかっているわけでも、過去問を分析できていたわけでもないため、実際の試験で違う問題が出ると対応できないということになっていました。そりゃ不合格を続けますよね。
それを反省し、やり方などをAIと相談しながら、データベーススペシャリストの問題で、現行と変更後の仕様を色分けしたり、制約条件をハイライトしたりして、情報を視覚的に整理するようにして、過去問を分析するようにしました。
加えて、業務プロセスを「誰が、いつ、何を、どうする」という形で分解し、簡易的なフローとして頭の中でモデル化ことも練習しました。
でも、これって資格試験の問題という点で肩ひじ張って見ていたのですが、現状の業務でやってないか?とふと気づきました。
私の中で、資格試験と実際の業務がまったくリンクしていなかったんですよね。
こういうことに気づいて、改めて問題文の分析を進め、他の過去問でも同じような視点で見ることができるようになりました。
「制約条件」の意識
問題文中の「必ず〜する」「〜でなければならない」といった制約が、どのようなキー制約やNULL制約、あるいは業務ルールに繋がるのかを徹底的に洗い出すようにしました。
情報処理試験(だけではないかもしれないですが)では、こういった制約条件が解答に密接に絡むことが多く、その点を意識するだけで、解答を導き出すことがしやすくなります。
こういう視点で分析することで、今まで適当に問題を解いていただけのやり方、思考が変わっていく感じがしました。
この点の意識は非常に重要だと改めて思います。
もし共感いただけたら、あなたも明確な分解、制約条件の意識を持って、問題を解いてみてください!
壁3:知識の『応用力』と『表現力』の不足 — 知識を解答として昇華させる力

壁の正体
知識も論理的思考力もある程度ついてきたとしても、最後の壁は、その知識と思考力を、「採点者に伝わる適切な解答」として具体的に『応用』し、『表現』する力でした。
私の場合は、頭の中では分かっていても、それを適切な専門用語で、かつ論理的に記述することができませんでした。SQLも、業務要件を正確に満たす形で最適化されたものを書く力が不足していました。
模範解答が複数ある問題で、「なぜどちらも正解なのか」が理解できなかったことも多々あり、結局本質的なところが理解できていなかったことが壁となっていたということです。
なぜこの壁ができたのか(自己分析)
この壁ができた理由を自己分析してみたところ、以下の2点が挙げられました。
「アウトプットの練習不足」
知識を「記述する」「SQLとして表現する」という実践的なアウトプットの絶対量が足りていませんでした。
問題は解いてみるのですが、薄い知識を基に問題をただ解いているだけで、アウトプットにはなっていなかった気がします。
アウトプットできていないまま、自分はできるはずだ、と無意識に思い込んでいたような気がします。
本来の意味でのアウトプットをして、理解を深めていくということができていなかったので、この壁ができてしまった一因なのかなと思います。
「採点基準の意識不足」
採点者が何を求めているのか、どういう記述が評価されるのかという視点が欠けていました。
これは、そういう視点をまったく持たず、問題文を読んでただ解答をひねり出していただけということです。
シラバスをちゃんと読んでいなかったこともそうですし、問題文の裏にある採点者の意図も読み取る気なし!
これを何年も続けていたら、そりゃできなくなるし、できないやり方が定着しますよね。
この壁を乗り越えるアプローチ
「ゼロから再現」からの「添削と改善」
この壁を乗り越えるために、何をすればいいのかを考えた時、何をすればいいのかを自分だけでは導き出せないというか、染みつきすぎて無理だったので、AIに聞いてみることにしました。
その答えは、自分で解答を書き出した後、模範解答と徹底的に比較し、何が足りなかったのか、どう表現すればより適切だったのかを分析することでした。
特に、記述問題では、模範解答の「キーワード」「接続詞」「論理の展開」を参考に、自分の言葉で再記述する練習を繰り返せと。
加えて、午後2の問題文を読みながら、概念データモデルと関連スキーマを0から作り出すことにトライすることも提案されたので、現在実施中です。
ゼロからの再現は始めた時、全然できませんでした。
AIの指示としては、問題文にある、概念データモデルと関連スキーマを一切見ず、文章から全てを抽出するというものだったので、エンティティ名は大体抽出できるのですが、属性を導き出すのが難しかったです。
「~を識別する」は主キーを示していたり、「設定する」「記録する」は属性を示したいたりと世の中で言われているパターンから導き出すことはできます。でもここまで。
なぜならこれ以上の深入りを今までしてこなかったからです。
AIに聞きながら、主キーを示すものが「~を識別する」だけではなく、いろいろあったり、属性を導き出す表現などを教えてもらいながら、少しずつ取り組んでいます。
そうすると問題の裏にある意図なども少しずつわかるようになってきた気がします。
こんな勉強の仕方を無意識に避けてきたので、だいぶ苦しみながらやってますが、新鮮な感じがして少しだけ楽しんで実施できています。
「異なる表現での試行」
これもAIに聞いてみて実施していることですが、解答に対して、そのままを見るだけだとわかったつもりになってしまい、過去のやり方に戻ってしまって、結果、ちゃんと理解できていないままになってしまう。
これを防ぐために、SQLであれば、同じ結果を得るために別の書き方を試してみる。
記述であれば、別の言葉で同じ内容を表現してみることで、表現力を高めるというのを練習するようにしました。
これを繰り返すと、わかったつもりで実施していた過去問の答えが、徐々に正解に近づくようになりました。
普通のことと言えばそうですが、凝り固まった私の頭で、これも気が付かずに解答を見てわかったつもりが、違う表現にすることをして、「考える」ことで違う刺激を脳に与えることで、理解が進んだ気がします。
もし共感いただけたら、ぜひ自分で解答をゼロから再現し、模範解答との徹底比較と改善を繰り返してみてください。
そして、異なる表現で試行することで、あなたの応用力と表現力が飛躍的に向上すると思います!
「3つの壁」を乗り越えるための共通戦略:量より質、そして戦略的休息

これまでの学習の反省
私が以前陥っていた「量にこだわる」「休日に遅を取り戻す」といった勉強法は、結果的にこれらの壁を高くし、乗り越えることを困難にしていたと思います。
特に「傷つきの回避」という心理が、効率の悪い学習を正当化し、真の課題に目を向けさせなかったのかなと今は思ってします。
なぜ、私は効率の悪い学習を続けてしまったのか? なぜ、真の課題から目を背けてしまったのか? その根底には、『お前、わかってないな』と誰かに思われることへの、強い『恐れ』があったことに気づきました。
下手なことを言って『ダメだな』と思われること。質問して『そんなことも知らないのか』と呆れられること。あるいは、必死に勉強して不合格になった時に、『やっぱりお前は頭が悪い』と自分自身が気づいてしまうこと。
この『評価不安』こそが、私の行動を無意識に制限し、真に困難な『アウトプット』や『深掘り』から逃げさせていたのです。
資格試験の勉強が「あまりできなかった」と言い訳を用意したり、なんとなく勉強した気になって深掘りを避けたりしていたのも、この恐れから自分を守るための、無意識の『自己妨害』だったのだと、今でははっきりと理解できます。
私のようなHSP気質を持つ人間にとって、他者の評価や反応は、想像以上に心に深く刺さるものです。
だからこそ、この『恐れ』が、私の学習を無意識のうちに停滞させていたのだと痛感しています。
不合格を正当化しているのですから、合格するわけがないですよね。
しかも、私自身、人の目をすごく気にしてしまう質で、しかもこの歳まで資格試験に受からないことへの引け目があったのも事実です。
新しい学習哲学
今まではただ時間をかけてやれば、成果が出ると思い込んで勉強をしていました。
しかし、それは間違いで、「毎日少しでも、質の高い学習を継続する」ことの重要性にずっと気づかずにやっていた結果でした。
仕事で疲労していようが、風邪を引いて体調を崩そうが、なんとなく平日にできなかった(しなかった)勉強を休日に無理にやっていてました。
でも、それはただ無駄に時間を消費していただけで、身になっていなかったのは明白です。
「集中力が切れたら潔く休む」という「戦略的休息」が、いかに学習効率と持続性を高めるかを、AIとの対話の中で学びました。
今でも、今日の勉強計画や、実施結果などをAIに報告してアドバイスをもらっています。
自分ひとりで考えるより、客観的な意見をもらえるので、凝り固まった考え、思考があると感じている人には有効な方法なのではないかと思います。
疲労回復については、私はHSP気質であることもあって、真剣に考えないと勉強効率が異常に下がってしまうことも体感しました。
HSP気質はストレス耐性が低く、いろいろな情報を無駄に受け取ってしまうので疲労しやすいです。
なので、私と同様にHSP気質だと思う人は、疲れたなという感覚を得たら、勉強を諦めて休むことがとても大事です。
それを押して無理に勉強することは、大きなマイナスになるという意識が大事だと思います。
「わかったつもり」から「ゼロから再現できる」へ
私と同じような過ちを犯してしまっている方含め、このコンセプトこそが、3つの壁を打ち破り、合格への道を切り開く鍵であると思っています。
ゼロから再現できるということは、しっかり理解できているということになるので、この点を意識してしっかり勉強していこうと思っています。
次回予告:実践!私の学習ルーティンと時間管理術
今回で「3つの壁」の正体を明らかにし、乗り越えるべき課題を明確にしました。
次回は、これらの壁を実際に乗り越えるために、私が日々の生活にどのように学習を組み込み、時間管理や疲労管理を行っているのか、具体的なルーティンや工夫について詳しくお話しします。
また次回!


