はじめに:あなたの努力が報われない真の理由

前回の記事では、50代からの「学び直し」を決意した僕(私)が、資格試験への挑戦を諦めていた中でAIとの出会いが転機となった経緯についてお話ししました。
まだ前回の記事を読まれていない方は、こちらからご覧いただけます。
そして、それらの根本原因が、具体的な「3つの壁」として私の前に立ちはだかっていたことを予告しました。
今回は、その「3つの壁」の正体を一つずつ具体的に掘り下げていきます。私が実際にどのようにその壁に直面し、そしてどのように乗り越えようとしているのか、具体的なアプローチとともにお伝えします。
これらの壁は、私同様に資格試験に悩んでいる方の参考になるものだと思って公開します。
壁1:知識を「使う」練習の欠如 — 「わかる」と「できる」の深い溝

あなたは、問題文を読んでいるはずなのに、なぜか設問の意図が見えてこない…そんな経験はありませんか?
分厚い参考書を読み込んだはずなのに、なぜか記述問題になると手が止まる。SQLが書けない。そう感じていませんか?
それが今回紹介する壁の1つ目の中心です!
壁の正体
この壁は、私が最も陥っていた「インプット過多」の学習法によって生み出されました。
参考書を読み込み、studyingの講義動画を見て「なるほど、分かった!」と頭では理解したつもりになるのですが、実際に午後問題を解こうとすると、知識が「使える」状態になっていないため、手も足も出ない。これが「わかる」と「できる」の間に横たわる深い溝です。
午前問題は、問題自体を解答と共に覚えることで6割の合格ラインを超えることができるため、このやり方で全部いいと思っていました。これが大きな失敗でした。
具体的な例として、「ER図の概念は理解しているのに、問題文から自分でER図を描けない」「SQLの構文は知っているのに、業務要件に合った複雑なSQLを書けない」といったものになります。
これでは午後の問題に太刀打ちできるわけないですよね。
なぜこの壁ができたのか(自己分析)
この壁を作り出したのも当然私なのですが、その要因を分析すると以下になると思っています。
「インプットの安心感」
網羅的な知識を頭に入れることだけに集中し、それが「勉強した」という満足感に繋がっていました。
これは結局無駄に時間をかけるだけで、やった感を出していただけでした。過去、学生時代にも同様の勉強法で実施していたのを思い出しました。これで大学受験も1回失敗したのも頷けます。
「アウトプットの負荷回避」
知識を「使う」ためのアウトプットは脳に高い負荷がかかるため、無意識に避けていました。
インプットした後、午後問題でしっかりアウトプットしないといけないのですが、この作業が結局つらいのいでやらずになんとかしようと(無意識に)していたのだと思っています。
よくよく考えると資格試験に受かるためには、これを乗り越えないといけないのですが、苦手なんですよね、結局。
壁2:論理的思考の練習不足 — 問題文の意図を正確に読み解く力
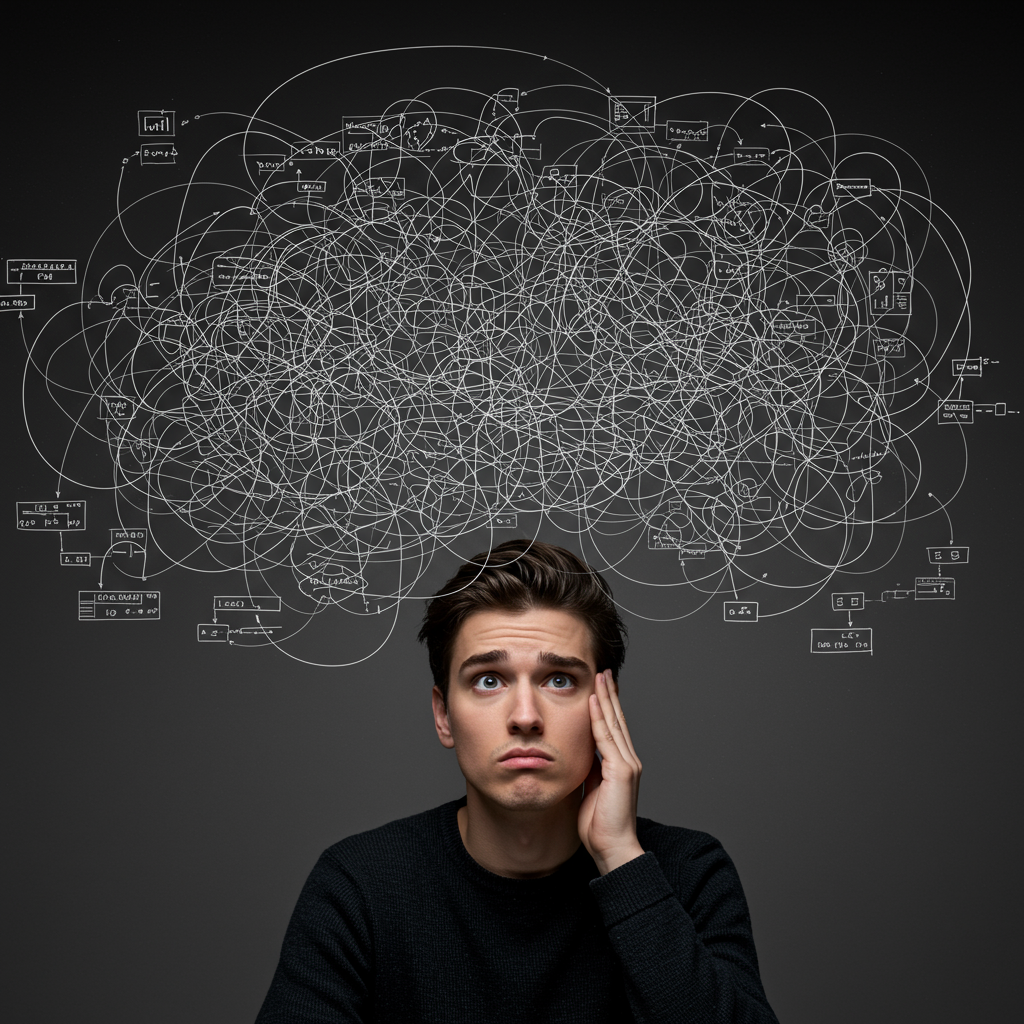
壁の正体
データベーススペシャリスト試験の午後問題は、単なる知識問題ではありません。
長文の問題文から、隠された業務要件、制約条件、矛盾点などを正確に読み解き、論理的に整理する高度な思考力が求められます。
私の場合は、問題文を「なんとなく」読んでしまい、表面的な情報しか捉えられていなかったため、出題者の意図を正確に理解できていませんでした。
具体的な例として、「現行システムの問題点から、変更後の設計にどう繋がるかが見えない」「複雑な業務フローをデータベースの構造に落とし込めない」といったことが挙げられます。
なぜこの壁ができたのか(自己分析)
この壁ができた理由を自己分析してみたところ、以下の2点が挙げられました。
「深読みの欠如」
問題文の情報を鵜呑みにし、行間を読む、裏に隠された意図を推察する練習が足りませんでした。
ただただ問題文を読み、設問に記載のある文字からピンポイントにその文字があるところのまわりだけ読んで解答をなんとなく組み立てるということをしていました。
このことが結果的に私が解答したものと、模範解答とのギャップになり、結果間違う、もしくは薄~い、曖昧な解答になって、答え合わせをした時にしっくりこない状態になってました。
しかも、それを深めていないで、次の問題に取り組んでいたので、わからないまま、わかったつもりで終わっていたのが現実でした。
「情報整理の不得手」
これは、複雑な情報を分解し、構造化して考える習慣がなかったことが原因で苦手になってしまったということです。
長文の最初に方と後の方に書いてある内容の紐づけなど、意識して読んだことがなかったこともあり、整合性が合っていない解答をし続けていました。
そういう読み方、解答の作り方を習慣的に実施できている人に取っては、当たり前のことなのかもしれません。
でも私にはそれがとても難しく、だんだん午後の長文を読むこと自体が嫌になっていきました。
壁1のアウトプットの負荷回避もこの辺りから発生していたような気がします。
壁3:知識の『応用力』と『表現力』の不足 — 知識を解答として昇華させる力

壁の正体
知識も論理的思考力もある程度ついてきたとしても、最後の壁は、その知識と思考力を、「採点者に伝わる適切な解答」として具体的に『応用』し、『表現』する力でした。
私の場合は、頭の中では分かっていても、それを適切な専門用語で、かつ論理的に記述することができませんでした。SQLも、業務要件を正確に満たす形で最適化されたものを書く力が不足していました。
模範解答が複数ある問題で、「なぜどちらも正解なのか」が理解できなかったことも多々あり、結局本質的なところが理解できていなかったことが壁となっていたということです。
なぜこの壁ができたのか(自己分析)
この壁ができた理由を自己分析してみたところ、以下の2点が挙げられました。
「アウトプットの練習不足」
知識を「記述する」「SQLとして表現する」という実践的なアウトプットの絶対量が足りていませんでした。
問題は解いてみるのですが、薄い知識を基に問題をただ解いているだけで、アウトプットにはなっていなかった気がします。
アウトプットできていないまま、自分はできるはずだ、と無意識に思い込んでいたような気がします。
本来の意味でのアウトプットをして、理解を深めていくということができていなかったので、この壁ができてしまった一因なのかなと思います。
「採点基準の意識不足」
採点者が何を求めているのか、どういう記述が評価されるのかという視点が欠けていました。
これは、そういう視点をまったく持たず、問題文を読んでただ解答をひねり出していただけということです。
シラバスをちゃんと読んでいなかったこともそうですし、問題文の裏にある採点者の意図も読み取る気なし!
これを何年も続けていたら、そりゃできなくなるし、できないやり方が定着しますよね。
まとめ:この「3つの壁」に気づくことが、合格への第一歩

今回で、データベーススペシャリスト試験の合格を阻んでいた「3つの壁」の正体と、なぜ私がその壁にぶつかってしまったのかを具体的に掘り下げてきました。
「知識を『使う』練習の欠如」「論理的思考の練習不足」「知識の『応用力』と『表現力』の不足」 これらは、決してあなただけの問題ではありません。
私と同じように、多くの資格試験学習者が直面し、努力が報われないと感じてしまう根本原因です。
この壁の正体に気づき、なぜそれが生まれたのかを自己分析することこそが、合格への第一歩となります。 自分の弱点や課題を正確に把握できれば、次に「どうすれば乗り越えられるか」という具体的な解決策が見えてくるからです。
次回、【第3回】合格を阻む「3つの壁」を乗り越える!50代HSPが実践する学習戦略では、今回明らかになった「3つの壁」を、私が実際にどのように乗り越えていったのか、具体的なアプローチと実践的な学習戦略について詳しくお話しします。
あなたの努力が報われるその日のために、ぜひ次回の記事も参考にしてください。また次回お会いしましょう!


