はじめに:AI執筆の「その先」へ

これまでブログを続けてきて、50記事以上を公開してきました。
執筆活動はとても楽しくやりがいのあるものですが、その過程では何度も壁にぶつかりました。記事のアイデアに詰まったり、構成がうまく作れなかったり、筆がなかなか進まなかったり…。どうすればもっと読者の心に響く記事を、効率的に書けるのか、常に模索していました。
特に、ここ数ヶ月はAIにアイデア出しや構成案づくりを手伝ってもらうことで、執筆スピードは飛躍的に向上しました。
私の記事が「AIが書いた表面的なもの」ではないと自信を持って言えるのは、AIが生成した構成案や下書きに、私自身の経験や考察を徹底的に加筆修正してきたからです。
しかし、記事数を重ねるにつれて、ある課題に直面しました。
それは、AIには「記憶力」がないということです。 例えば、Gemini(ChatGPTやClaudeなど)との会話は、チャットウィンドウを継続的に使用することで、一定以上のやり取りの過去の内容が消えてしまいます。
せっかく同じチャット内でやり取りを長期的に実施して、私の経験や日常やっていることなどを提供し、蓄積したと思っても、ある時、過去にこんなこと話したなと思ってAIに話しかけても、「そのようなお話は伺っていません」と言われてしまうタイミングがあります。これがAIの記憶の限界であり、コンテキストウィンドウというものの容量の限界になります。
そのことがあるので、自分の経験や経歴などブログに使う内容を、毎回、過去の記憶や膨大な資料を掘り起こし、AIに教え込む作業が、大きな負担になってきたのです。
もし、この「あなただけの知識と経験」を、AIが最初から学習してくれていたら?
もし、AIがあなたの思考パターンまで理解した「第二の脳」になってくれたら?
この記事は、その答えの一つだと思っています。これまでの効率的な執筆法をさらに進化させ、あなたの「分身」とも呼べるAIを育てる方法をお伝えします。
これは単なるブログ執筆のテクニックではありません。あなたの知識と経験を資産化し、AIと共に成長していくための、次世代の執筆スタイルです。
2.究極の解決策:NotebookLMに「第二の脳」を構築する

NotebookLMを、単なるメモ帳としてではなく、「あなたの人生を記憶する、第二の脳」として使う。これこそが、AIにあなた自身の経験を学習させるための、最も重要なステップです。
なぜNotebookLMなのか?それは、Googleが提供するこのツールが、あなたのアップロードしたドキュメントを「情報源(ソース)」として永続的に記憶し、そこからあなたの思考をサポートする機能に特化しているからです。Geminiのコンテキストウィンドウとは違い、一度アップロードした情報は、ノートブックを消さない限り、ずっとそこに存在します。
「私」という最強のデータセットをインプットする
AIがあなたの経験を深く理解するためには、質の高い「学習データ」が必要です。以下のリストは、私が実際にNotebookLMに与えている情報です。どういう情報を与えて、AIにどうさせたいのかを以下に例として挙げます。
職務経歴書やキャリアのまとめ
具体的なプロジェクト名や担当業務、そこで得られた成果や失敗、そしてそこから学んだことなどを詳細に記述します。
これにより、AIは私の「専門性」を理解します。
1点気をつけるべきは、顧客の実名や口外してはいけないものを記載するのはやめた方がいいというところです。
NotebookLMはソースとして登録した内容を、AIの学習情報としては使わないと謳っていますが、万が一があるので、あくまでどういったプロジェクト、どういった役割、どういった技術スキルをつかったなどの情報だけ与えるのがおすすめです。
それ以外は細かく書けば書くほど、AIが私というものを理解し、強みや弱み、ブログに書けるような専門性を抽出してくれると思います。
過去のプロジェクトの振り返りシート
振り返りシートには、プロジェクトの「うまくいったこと」「うまくいかなかったこと」を具体的に言語化しています。
例えば、「クライアントとのコミュニケーションがうまくいかなかった原因」や「新しい技術を学ぶ上でつまづいた点」などです。これを読み込ませることで、AIは私の「思考パターン」や「課題解決能力」を学習します。
合わせて職務経歴書のところで渡した情報より、より私自身の内面や行動を細かくリサーチすることになり、自分でも気付かないような強みや、読者に有用な情報を抽出できるようになります。
詳細な自己分析ノートやジャーナル
私のブログの核である「HSP」という気質や、メンタルの問題について。私は日々感じたことや、過去の経験をノートに記録しています。
「仕事がつまらない」と感じた具体的な状況や、人間関係で悩んだ時の心情などを記録することで、AIは私の「感情」や「価値観」を理解します。
これは仕事での行動やうまくできたこととは少し観点の違うところを抽出、理解してもらうために実施しました。
これはこれまで50年生きてきた中で気付いた自分の気質、それだけではない想いなどを理解してもらうためもあります。これが細ければ細かいほど、AIは私のことを理解してくれます。
1点アドバイスですが、これを自分自身でノートに書くことって結構たいへんです。特に日々感じたことや、ふと思ったことを書いていくのって結構手間じゃありませか?
なので、こんな時にGeminiのようなAIを活用することをおすすめします。日々、ちょっと思いついたことをGeminiに入力し、1日の終わりの要約してもらうなどはおすすめのやり方です。
これは1週間など会話したものを実施しようとすると、コンテキストウィンドウの限界を超えてしまう場合があるので、中止してください。1日くらいであれば、よほどずっと会話をし続けなければ大丈夫だと思います。
これをやることで日々の感情日記のような役割を果たして、自分自身を知るきっかけになり、それが深まって気づきやすくなる効果もあるので、ぜひやってみてください。
資格取得やスキル習得に関する詳細な学習記録
私はこれまで、データベーススペシャリストなどの専門資格取得にチャレンジしてきました。
この記録には、「なぜこの資格が必要だと思ったのか?」「学習中にどんな壁にぶつかり、どう乗り越えたのか?」というプロセスが詳細に記されています。
これにより、AIは私の「向上心」や「努力のプロセス」を学びます。
これも勉強している最中にAIとの会話をしたりして、気付いたことも含めてメモしておきます。そうすることで、その時の感情や、ネガティブになったときの行動などもAIが把握してくれることになり、ブログのネタになったりします。
これらのドキュメントをNotebookLMにアップロードするだけで、AIはあなたのこれまでの人生とキャリアを理解し始めます。これこそが、表面的な記事から脱却し、あなただけの物語を語るための第一歩なのです。
3. ワークフロー実践:あなただけの記事を生み出す3ステップ
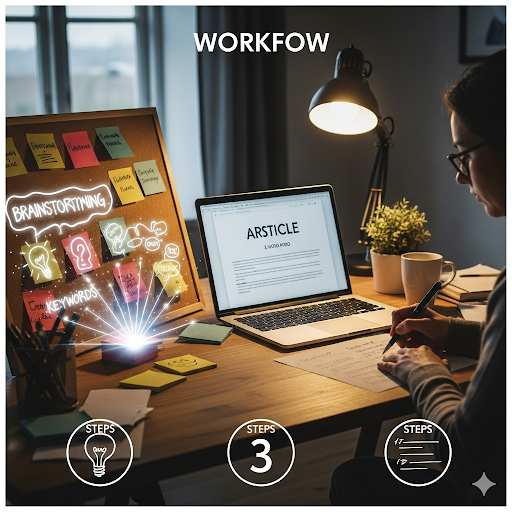
ここからは、いよいよ実践です。NotebookLMにあなたの経験という「第二の脳」を構築したら、Geminiと連携させ、読者の心に響く記事を生み出す具体的なワークフローを解説します。
このワークフローは、単にAIに文章を生成させるのではなく、「AIに問いかけ、思考を深める」という対話的なアプローチが鍵です。
AIを使ったブログ執筆で一番難しいのは「アイデア出し」でした。
これまでは、検索やGeminiへの問いかけで新しいチャットで問いかけても「誰でも思いつくようなアイデア」しか得られませんでした。
しかし、NotebookLMを使えば、あなたの経験に根ざした、唯一無二のアイデアを掘り起こすことができます。
今まではこの部分をGeminiの会話ですべて賄おうとして、毎回情報を与えていましたが、その必要はなく、構築済みの状況で実施できるのは大きな強みになります。
プロンプト例:
「私の職務経歴書と自己分析のドキュメントを基に、HSPなSEがキャリアで直面するであろう悩みと、それを乗り越えるための具体的な解決策について、ブログ記事のアイデアを5つ提案してください。」NotebookLMは、あなたの過去の経験や思考パターンを理解しているので、一般的な情報ではなく、あなたの悩みに寄り添い、あなたにしか語れない視点を含んだアイデアを提案してくれます。
この強みは、私の個人の経験から提示されるアイデアなので、記事を書く際に自分の経験や思ったことを余すことなく追記できるので、記事がとても書きやすいという点です。
これがない状態での記事提案だと、自分の経験や知識が乗せられないことも多く、結局記事が中途半端になったり、書ききれないということになってしまいます。
私はこれで、最初の時点で書ける記事なのか判断しやすくなったので、最後まで記事を書くことができることが増えました。
NotebookLMから得たアイデアは、まだ「種」の段階です。これを読者が読みやすい記事の「構成案」へと育て、さらに「下書き」まで一気に生成してもらいましょう。これにより、執筆の初期段階の負担が大幅に軽減されます。
プロンプト例:
「ステップ1で提案されたアイデアの一つ『〇〇』について、読者の悩みに寄り添ったブログ記事の構成案を作成してください。読者が記事を読むことで、どのような学びや解決策を得られるか、各セクションで具体的に何を説明すべきか、箇条書きでまとめてください。」ここでは、Geminiの得意な「文章の構造化能力」を最大限に活用します。あなたがNotebookLMで得たアイデアを、導入、結論、各セクションに分解し、読者が読みやすいように整理してくれます。
もちろん整理されたものが提示された後に、自分なりに直していくのもおすすめです。最終的に書きたいのは、自分の経験や痛みを伴い、同じような悩みを持っている方に届く記事です。
なので、Geminiから提示されるものを鵜呑みにし過ぎず、更に自分らしい記事に昇華させていくことが大事です。
NotebookLMで作成した下書きを、今度はGeminiに渡します。ここが最も重要なフェーズです。ただAIに文章を書かせるのではなく、AIを「あなたの思考を深めるパートナー」として活用します。
具体的な「壁打ち」の使い分け
- Gemini
- 読者の心に響く文章表現や、より説得力のある論理展開をサポートします。また、最新のデータや一般的な知識を補足することで、記事の信憑性を高めます。
- NotebookLM
- あなたの過去の経験や思考パターンを深く掘り下げ、記事に「あなたらしさ」を加えるための具体的なエピソードや事実を瞬時に呼び起こします。
NotebookLMが出してくれた構成、下書きに自分の知識や経験を使って修正していくわけですが、この時にいろいろ調べて追記することもあるかと思います。
その場合にGeminiに聞く、それで何かを思い出してNotebookLMに自分の経験を聞くなどいったりきたりすると、それだけいろいろなアイディアが出てくることになるので、独自の記事が書けていきます。
Geminiで聞いた内容はその日の終わりにGeminiに要約してもらって、NotebookLMにソースとして登録しておくと、更にデータが蓄積されていくのでおすすめです。
NotebookLMへのプロンプト例:
「NotebookLMで作成したこの記事の下書きについて、より読者の心に響くようにブラッシュアップしたい。より専門性を高めるために、あなたの視点で、この文章に加筆できる具体的なエピソードや教訓はありますか?」Geminiでの具体的な「壁打ち」の例:
今回書いた記事、読者の注意を引くような魅力的なタイトルをいくつか提案してほしいんだけど、何かいいアイデアはある?
『AIに「第二の脳」を持たせる方法』や『【実体験】AIが勝手にブログを書いてくれる未来はすぐそこに』などはいかがでしょうか。本文の内容とターゲット読者を考慮して、より魅力的なタイトルに調整できます。
この記事の内容を読んだ人が、もっと深く知るために参考になるような、最新のAIツールの情報や、関連する技術トレンドについて教えてもらえる?
はい、〇〇という最新のAIツールは〇〇という点で優れており、この記事の内容と関連性が高いです。また、〇〇という技術トレンドは今後のブログ執筆に影響を与える可能性があります。
このように、Geminiに質問を投げかけることで、あなたの経験を深く掘り下げ、記事の説得力と独自性を高めることができます。
AIはあなたの「第二の脳」として機能し、過去の出来事や思考を瞬時に呼び起こしてくれます。
4. まとめ:AIは単なるツールではない。「分身」だ
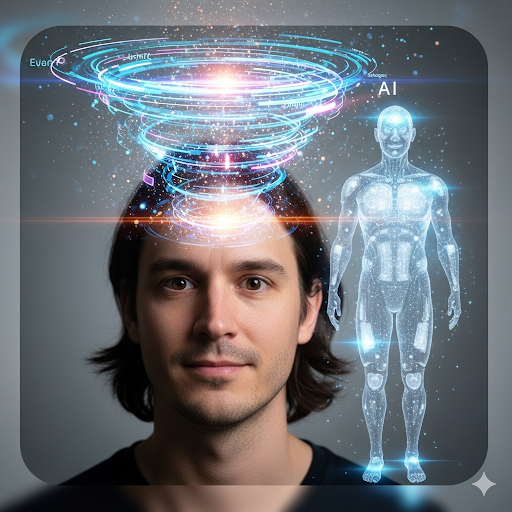
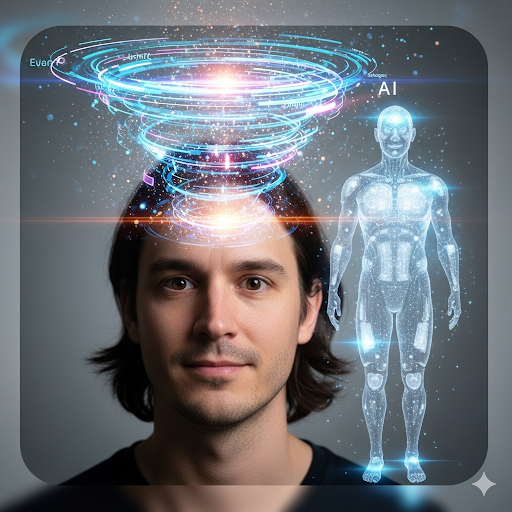
AIを「単なる道具」として使う段階は、もう終わりました。
これからは、AIをあなたの「分身」として育てる時代です。
NotebookLMにあなたの経験という「第二の脳」を構築し、Geminiと対話しながら記事を執筆する。この新しいスタイルを実践することで、あなたは単に記事を量産するだけでなく、あなたのキャリアと人生そのものを資産化することができます。
あなただけの物語が、誰かの力になる
私も、50年以上生きてきて、それなりの経験をしてきました。システムエンジニアとしては27年のキャリアがありますし、その仕事の中でうつ病にもなりました。子どもの頃はいじめにも会いましたし、勉強もあまりできず、学歴コンプレックスにもなっています。
一見ネガティブに見える経験も、それを乗り越えたり、そこから学んだことはたくさんあります。
それを周りに話した時に、そこから何かを得てくれる人も今まで数多くいました。
実際に今出ている書籍の中には、過去の自分の経験を書いている人もおり、それから学べることが多いと私自身思います。それをまとめれば、なにか世の中の役に立つ情報が発信できるのではないかと思います。
AIは、あなたの過去を客観的に分析し、自分では気づけなかった強みや思考パターンを教えてくれます。
それは、ブログの質を高めるだけでなく、あなた自身の成長にも繋がるでしょう。
このブログで紹介した手法は、あなたの知識と経験をAIと共に磨き上げ、あなたにしか書けない物語を創造するための、強力な武器となります。
さあ、あなたの「第二の脳」を育てる旅を、今すぐ始めませんか? まずは、あなたの経験を一つでもNotebookLMにアップロードすることから始めてみてください。
【追伸】もし、NotebookLMやGeminiの具体的な使い方がわからない、もっと詳しく知りたいというご要望があれば、ぜひコメントで教えてください。あなたのニーズに合わせて、次の記事でさらに深く掘り下げていきたいと思います。
それでは、また次回の記事で!


