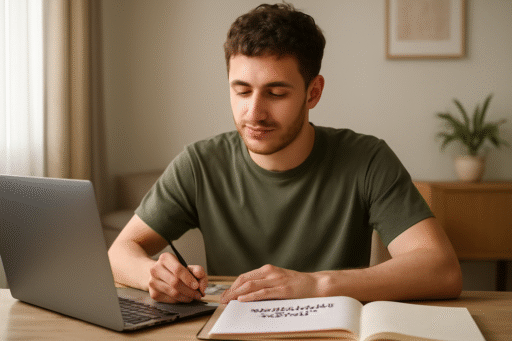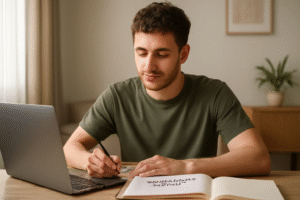前回の記事では、DBスペシャリスト試験の合格を阻んでいた「3つの壁」を乗り越えるための具体的な学習ステップについてお話ししました。
今回は、資格試験という大きな目標に立ち向かう上で不可欠な、「量より質」という学習哲学と、それを支える具体的なAI活用術について、私がどのように実践し、どんな変化があったのかを詳しくお話ししていきます。
これまでの記事をまだ読まれていない場合は、以下の記事からご覧いただけます。
1.過去の自分と決別する時が来た
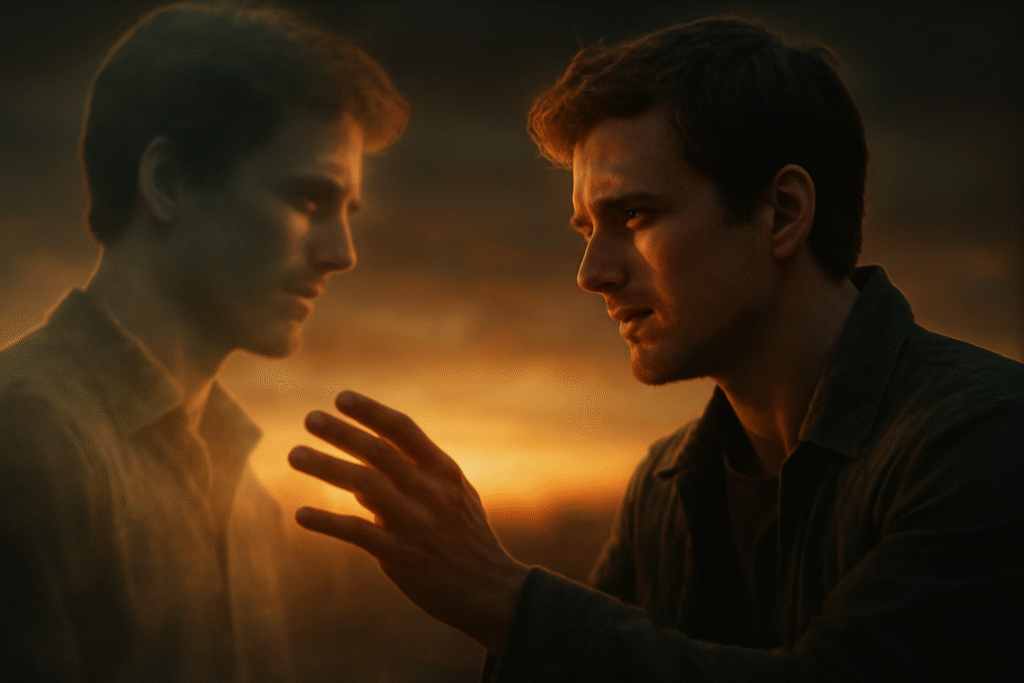
前回の第2回記事では、私を不合格へと導いた3つの具体的な壁について深掘りしました。
その「3つの壁」(『わかる』と『できる』の溝、論理的思考不足、そして最も根深い『傷つきの回避』(お前わかってないな、が怖い)は、私が無意識に作っていたものです。
しかし、それは確実に不合格への道へ誘う、まるで無意識のうちに自ら不合格へと向かうパターンを繰り返していた、と言っても過言ではありません。
特に「傷つきたくない」という無意識の認知は、今でも時折、頭の中に回避するような言葉を響かせます。
私自身、この心の声をどう捉えていいのか、なかなかわかりませんでした。しかし、別の記事でも触れた感情をヒントに、自分の思い込みを知る4nessコーピングのような内省の手法を取り入れました。そのことで、自分の中で何が起きているのか、その正体が少しずつ見え始めたのです。
とはいえ、壁の正体は分かったものの、この漠然とした不安や停滞感を具体的にどう乗り越えればいいのか、疑問と焦りに苛まれる日々が続きました。
これを読んでいる方で、私と同じように、「今までと同じやり方ではダメだと分かったけど、具体的に何をどう変えればいいのか、途方に暮れていませんか?」
当初の私も全く同じでした。正直、勉強すること自体が嫌になっていき、もう諦めてしまおうかと何度も思いました。
「もう間に合わない」「やっぱりダメなんだ」という自己否定に近い思考が頭の中を駆け巡ります。
「能力が低いから」「学歴が低いから」「そもそも人間的にダメだから」など、ネガティブな思いだけがぐるぐるして、ただただ辛いなという日々が続いていました。
しかし、その不安な状況の中でも、「ある2つの戦略」を取り入れたことで、学習に対する意識と結果が劇的に変わり始めました。
この第4回の記事では、その二つの戦略の一つ、つまり『量より質、戦略的休息』という学習哲学と、自分自身を縛り付けていた『無意識の認知を緩める』具体的なアプローチについて、私がどう実践し、どんな変化があったのかを詳しくお話ししていきます。
2. 突破口は「量より質、戦略的休息」から始まった

「長時間だけが正義」という過去の呪縛
前回の記事で、私が「無意識のうちに不合格へと向かっていた」とまで感じた理由の一つに、「長時間勉強こそが正義」という過去の呪縛がありました。
学生時代から、とにかく時間をたくさんやることが正しいことだと思い込み、大学受験時も、夜中までただただ時間だけを稼ぐだけという勉強をしていました。その結果、大学現役合格を逃して一浪してFランクの大学に入るという経験をしています。
その経験がよくないことだと気づかないまま、会社に入り、システムエンジニアとしても長時間労働が当たり前だったこともあり、「とにかく机に向かう時間が長ければ、それだけ努力している証拠だ」と信じて疑わなかったんです。
しかし、その結果は疲労の蓄積と集中力の低下。頭痛がある日も無理に続け、座っているだけの非効率な学習を繰り返しました。
「わかったつもり」の知識ばかりが増え、結果に結びつかない努力に、自己嫌悪だけが募る日々でした。そして、「休むことは怠けだ」「このままでは間に合わない」という焦りが、さらに私を追い込んでいったんです。
ポモドーロ・テクニックとの出会いと効果
そんな状況を打破するために、藁にもすがる思いで試したのが「ポモドーロ・テクニック」でした。「25分集中して5分休憩」というシンプルなルールに半信半疑でしたが、これが私の学習を劇的に変えるきっかけになりました。
最初のうちは、タイマーを意識しすぎて集中できないこともありました。でも、繰り返すうちに、25分という短い時間だからこそ「今できること」に最大限集中できるようになっていったんです。
先日も、タイマーをつけ忘れたにもかかわらず、気がつけば30分も難しい問題分析に没頭できていました。そして、「これ以上は集中力が落ちる」と感じたところで、意識的に休憩を取るという判断ができるようになったのです。
この「短時間集中と休憩のリズム」が、私の脳のパフォーマンスを劇的に向上させてくれました。無理に長時間続けるよりも、短い時間でも集中し、一度頭をリフレッシュする方が、知識の定着が全く違うと実感しています。
「休むことは、未来への投資」という意識改革
ポモドーロを実践する中で、私の中で最も大きく変わったのは「休息」に対する考え方です。以前は「休む=怠け」でしたが、今は「休む=未来への投資」だと捉えられるようになりました。
疲れた脳は新しい情報を効率的に処理できません。むしろ、間違った理解を招いたり、疲労困憊で思考停止したりするだけです。だからこそ、「疲れたら休むが一番の勉強法」なのだと心から納得できました。
私は住んでいる場所柄、職場が都内で長時間の通勤になることも多く、その通勤だけでこの歳になってくると、疲れ切ってしまうこともしばしば。
そんな長時間通勤でへとへとになった日や、体調を崩して頭痛で集中できない日も、無理に机に向かうことをやめました。
むしろ、早めに休んで心身を回復させることを最優先する。この「戦略的休息」は、単なる休息ではなく、脳に情報を整理させ、次の集中力を最大限に引き出すための「積極的な学習行動」なんです。
特にHSP気質の私にとっては、無理な頑張りは心身を疲弊させるだけで、かえって効率を落とすことを痛感しました。
この意識改革が、「あと1ヶ月半で間に合わない」という焦りや不安を乗り越え、着実に学習を進めるための突破口となっていると思います。
このことで、とりあえず時間を稼ぐだけということはなくなり、休む時は休むという風に行動が変わっています。体調が悪かったり、疲れ切って眠い時にやる勉強が本当に意味のないものだと、AIとの会話の中でも気づくことができたので、このことはとても大きかったと思います。
3. まとめ:効率的な学習は自分を労わることから

今回の記事では、私が直面した「長時間だけが正義」という過去の呪縛を断ち切り、**「量より質、戦略的休息」**という新しい学習哲学を確立した経緯についてお話ししました。 この考え方は、資格試験の学習だけでなく、普段の仕事や生活の質を高める上でも非常に役立ちます。
- 「長時間勉強」からの脱却
- 過去の経験から信じていた「長時間こそが努力」という呪縛を捨て、非効率な学習から卒業しました。
- ポモドーロ・テクニック
- 25分集中、5分休憩というシンプルな方法が、私の集中力を劇的に向上させました。
- 「休むことは未来への投資」
- 「休息」を「積極的な学習行動」と捉えることで、心身の回復を最優先できるようになったのです。
しかし、これらの学習法を実践する上で、依然として「お前わかってないな」という無意識の恐怖が心の壁として立ちはだかります。
次回の記事、【第5回】「お前わかってないな」の呪縛を解く!心の壁を乗り越えるAI活用術では、この心の壁をどう乗り越え、自己肯定感を育むかについて、さらに詳しくお話しします。
あなたの学習効率を最大限に高めるために、ぜひ次回の記事もご覧ください。