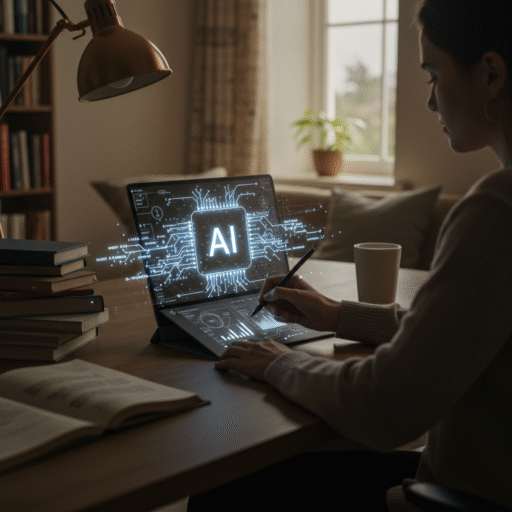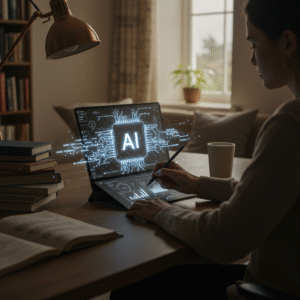はじめに:企画が固まれば、執筆は9割終わったも同然

前回の記事では、AIを「最高の壁打ち相手」にして、あなただけの「知のデータベース」を構築し、そこから具体的な記事の「企画案」を作成する方法を解説しました。
まだ前回の記事を読んでいない方は、ぜひこちらからご覧ください。
関連記事: 【第1回】AIと二人三脚!ネタ切れしない「企画力」の身につけ方
記事の企画が固まった今、あなたはすでにブログ執筆の最大の壁を乗り越えています。
なぜなら、ブログの執筆において最も時間がかかり、精神的なエネルギーを消費するのは、実は「何を書くか」を考える部分だからです。悩んでいるうちにめんどくさくなって、公開を断念ということが一番多いと思います。
これからは、AIを「優秀なライター」として活用し、あなたの思考と個性を反映した記事を効率的に生み出していきましょう。
企画が固まっても、いきなり白紙の画面に向き合うのは大変ですよね。
まずはAIに、記事全体の「骨格」となる見出し構成を作ってもらいましょう。これは、読者もあなたも迷わない、記事の道筋を明確にする大切な作業です。
1.全体構成の指示
前回の企画案を元に、ブログ記事の詳細な見出し構成(H2、H3レベル)を提案してください。
【企画テーマ】今さら聞けないを解決する!50代SEのAI活用術
【ターゲット読者】IT業界で長年の経験を持つが、新しい技術や知識に漠然とした不安を感じている50代のSE。
【記事の目的】読者がAIを『今さら聞けない』を解決する頼れる相棒として認識し、実際に活用したくなるように促すこと。
【ざっくりとした構成】
1.導入:長年の経験を持つベテランSEが抱える『今さら聞けない』という葛藤に共感する。
2.本題:具体的なエラー解決の事例を挙げ、AIがどのように問題解決をサポートしてくれるかを解説する。
3.AIを活用することで、知識の更新が効率化され、自信を持って仕事に取り組めるようになることを強調する。(読者が最後まで読みたくなるように、魅力的なタイトルも考慮に入れてください。)
ポイント
- いきなり本文を依頼するのではなく、まず「骨格」を作ることで、書き手も読者も迷わない記事の道筋を明確にします。
- 詳細な見出し構成は、記事全体の流れと論理性を決める重要な設計図です。
2.「壁打ち」で構成を磨く
AIが提案した構成案に対し、さらに「壁打ち」を重ねて磨き上げましょう。
- 「この見出しの順序で、読者は自然に読み進められるだろうか?」
- 「もっと読者の心に響く表現や見出しの言葉はないか?」
- 「このセクションはもう少し深掘りしたいんだけど、どんな内容を追加できるかな?」
このようにAIと対話することで、読者の興味を引きつけ、離脱を防ぐための最適な構成を一緒に作り上げることができます。
記事の骨格が完成したら、いよいよ各見出しの下に本文のドラフトを生成させます。
一度に記事全体を生成させるのではなく、セクションごとに依頼するのが賢い使い方です。これにより、AIの生成精度が高まり、あなたの修正作業も格段に楽になります。
1.見出しごとの執筆指示
STEP1で完成した構成の各見出し(H2、H3)ごとに、AIに本文のドラフトを書いてもらいましょう。
以下のH2見出しについて、読者の共感を呼ぶ導入文を作成してください。
【ターゲット読者】:IT業界で長年の経験を持つが、新しい技術や知識に漠然とした不安を感じている50代のSEです。
【H2見出し】:今さら聞けない』の壁を壊す!AIがあなたの知識をアップデート
ポイント:
- AIに「完璧な記事」を期待するのではなく、あくまで「下書き」を生成してもらうというスタンスが重要です。
- セクションごとに依頼することで、AIがその部分に集中し、より的確な文章を生成しやすくなります。
2. あなたの「口調」をAIに学習させる
記事の品質を向上させるために、AIにあなたのブログの「トーン&マナー」を具体的に指示しましょう。これにより、AIが生成する文章が、よりあなたらしい口調に近づきます。
- 「私のブログは、読者に寄り添い、親しみやすい口調で語りかけるスタイルです。この記事のこのセクションを、そのトーンで書いてください。」
- 「読者からの質問に答えるような形で、会話調の文章にしてください。」
AIが生成した一次ドラフトは、いわば「骨格」です。
ここからは、あなた自身の経験と感情を加えて「血肉」を与えていきます。この作業こそが、記事を「あなただけのもの」にする最も重要なステップです。
1.「魂の肉付け」
AIが生成した各セクションのドラフトに対し、あなた自身の具体的な経験、感情、失敗談、成功談を追記しましょう。AIは一般的な情報しか提供できないため、あなたの体験こそが記事の独自性を生む最大の要素です。
具体的な肉付けの例:
- 導入文
AIが生成した一般的な導入文に、あなた自身の「今さら誰かに聞くのは恥ずかしい」という葛藤や、実際に感じたプレッシャーの経験を付け加えます。例えば、「初めてAIに質問した時、こんな簡単なこと聞いていいのかと内心ヒヤヒヤしました」といった具体的な心情です。
- 具体的な事例:
AIが「エラー解決」と書いている部分を、過去にあなたが直面した具体的なエラーコードや、その時に感じた焦り、そしてAIに相談した際のやり取りを詳細に記述します。「AIに〇〇というエラーコードを貼り付けたら、瞬時に解決策と原因候補を複数提示してくれたんです!」といった臨場感を加えます。
- 感情の描写:
「AIが分かりやすく提示してくれました。焦って闇雲に検索するよりも、AIに聞くことで『まずどこから手をつければいいか』が明確になり、解決への第一歩が驚くほどスムーズになるのを実感できます。」 このような、あなたが実際に感じた「感情」や「実感」を盛り込むことで、記事は一気に説得力と深みを増します。読者は、あなたの経験を通じて、AI活用の本当の価値を理解するでしょう。
2.「読者への問いかけ」の追加
記事の途中で、読者に「自分ごと」として考えてもらうための問いかけを適宜追加するのも効果的です。
- 「あなたも、こんな経験ありませんか?コメントで教えてくださいね。」
- 「このAI活用術、あなたの業務でならどう応用できそうですか?」
おわりに:執筆は「つらい作業」ではない!

AIを「優秀なライター」として活用することで、ブログ執筆は、「つらい作業」から「楽しい共同作業」へと変わります。
この共同作業をマスターすれば、もう「書けない」と悩むことはありません。
次回**【第3回】AIを「最高の編集者」にする!読まれる記事の仕上げ方では、完成したドラフトを、さらに磨き上げて読まれる記事にするための最終ステップを解説します。
タイトルや見出しの最適化、アイキャッチ画像の生成、SNS告知など、公開前の最終仕上げについて紹介します。