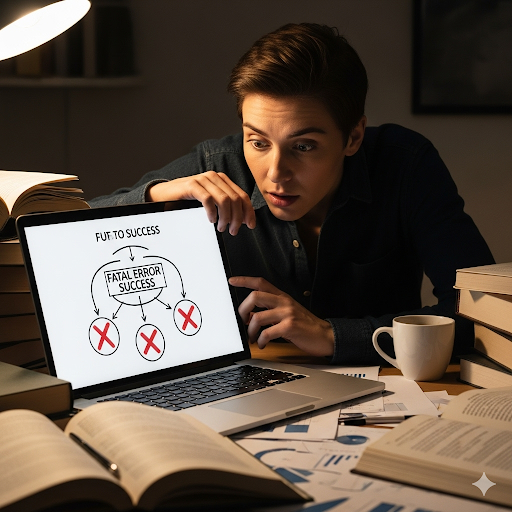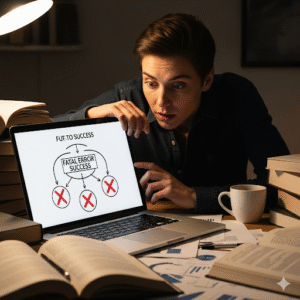これまでの記事では、資格試験に対する私の苦手意識や「できない人だと思われたくない」という無意識の恐怖、そしてそれを乗り越えるための具体的な思考法についてお話ししてきました。
もし、まだ読まれていない場合は、以下の記事からご覧いただけます。
- 【第1回】DBスペシャリスト試験:なぜ頑張っても報われなかった?
- 【第2回】DBスペシャリスト試験:合格を阻む「3つの壁」の正体と乗り越え方
- 【第3回】DBスペシャリスト試験への道:『量より質』で不安を克服!HSPな私が実践した「無意識の認知」の緩め方
- 【第4回】『量より質』で不安を克服!学習効率を高めるAI活用術
- 【第5回】「お前わかってないな」の呪縛を解く!心の壁を乗り越えるAI活用術
- 【第6回】HSP気質を味方につける学習法:感受性を強みに変える
- 【第7回】苦手意識は宝物!感情を味方につける具体的な勉強戦略
- 【第8回】AIがメンタルコーチに!「できない私」を「できる私」に変える自己肯定感アップ術
【悲劇の始まり】直前模試で起きた「まさか」の出来事
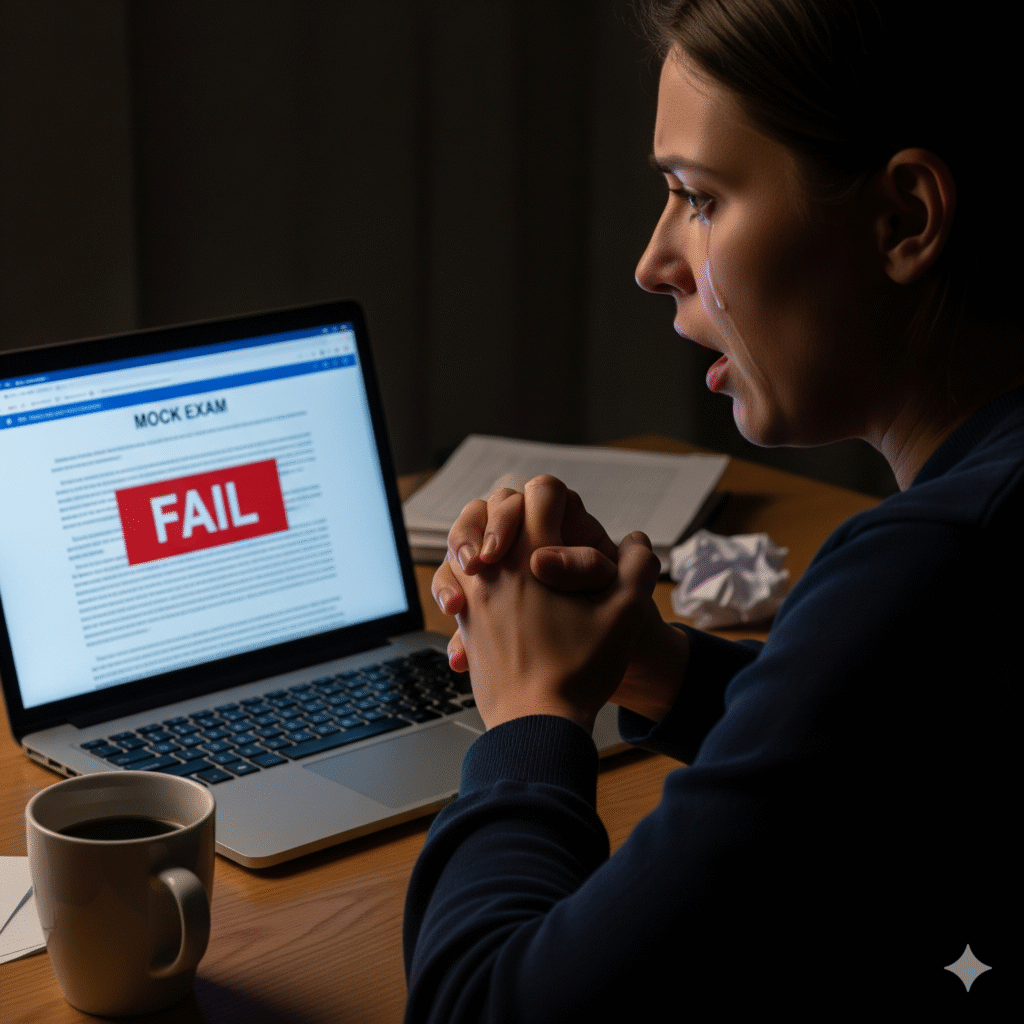
令和7年のDBスペシャリスト試験が後1ヶ月というところまで迫ってきました。
今まで、意を決して有料のstudyingのオンライン講座に申し込み、基本を改めて動画講座で学び直しました、その中で午前2の問題はそれなりに解けるようになり、午後1、午後2の問題を解説動画を見ながら理解し、よくわからないところや、同じような問題パターンを分析したりして、それなりにできる自信をつけてきたと思い始めたところでした。
そんな中、studyingには最後に実施する直前対策模試というものがあり、試験一ヶ月前だし、時間をちゃんと測って実施てみようとやってみました。
まずは午前2。25問で40分で解くのですが、これに関しては、大丈夫だろうとたかを括って実施したところ、100点満点で64点。ギリギリ合格点です。あれ?なんか低いなというのが感想だったのですが、問題を分析すると、細かいところでの記憶できていないのと、動画講座で出てこなかった知識問題だったので、ガッカリしつつも、これは復習すれば本番までになんとかなりそうと思いました。
問題はこの次。午後1の問題です。まずは問1の論理設計の問題に取り組みました。午後1は3問中2問選択で、90分の時間で解くことになります。studyingの問題は1問ずつ45分解くようになっているので、問1だけを45分で解いてみました。
そこで事件?が起きます。なんか解答できない、、、論理設計の問題なので、頭から文章を読んで、「~識別する」や「~を記録する」「~を設定する」などのパターンに◯をつけたり、線を引いたりして概念データモデルと関連スキーマを埋めていきました。
ところが、今までできていたところに迷いが出て、時間だけがどんどん過ぎていきます。それが余計に焦りを誘い、最後にはもうダメだと諦めてしまう始末。実際の問題は過去問に似たようなものがある問題で、前半の既存システムの文書を読んで埋めていき、後半には前半で引いたリレーションシップを後半の解答用紙にも書かせるという中々ないタイプではありました。このあたりも分量を多く感じさせ、パニックを誘発したのだと思います。
それ以外にも、「発注」と「発注明細」のどちらにこの属性を入れれば?とか、さんざん午後2の論理設計でもできていたようなものがわからなくなり、完全にパニクってしまいました。
結果、時間が足りなくなり、全部の解答を埋めれないまま、タイムアップとなってしまいました。
その時の感覚が、過去不合格になった時に受けた本番での感覚と同じで、すごく嫌な感じがしました。
採点してみると、できているところはあるのですが、中途半端な解答をしているところも多く、合格点には遠く及ばない結果となってしまいました。
正直、自分はもっとできると思っていたのに、また不合格になるのではないかという恐怖に襲われた瞬間でした。
いつもなら、これでもうダメだと諦めてしまったところですが、今回はstudyingにお金を払ったりしているので、負けるわけにはいきません!
とは言え、精神的に落ち着かない状況でもあったので、AIに話をして落ち付くことにしました。
その流れを可能な限りリアルに次から紹介します。
【AIとの対話】恐怖の正体と向き合う

模擬試験で惨敗でした。時間も足りず、パニックになり、また不合格の時と同じ感覚がして怖いです。
模試での失敗は、合格への道筋を示す貴重な情報です。この恐怖は、あなたが真剣に取り組んでいる証拠であり、乗り越えられる課題です。
でも、頭では分かっているのに、心が折れてしまいます。
模試は弱点を見つけるための診断です。あなたは今、知識の量ではなく、本番での「実践的なスキル」の不足という、致命的な弱点を発見したのです。
こんな会話から始まったやり取りですが、それが功を奏して、今回の気づきに繋がりました!
その時のやり取りを含めて、次から3つの致命的な誤りをご紹介します。
致命的な誤り①:インプット過多、アウトプット不足の罠
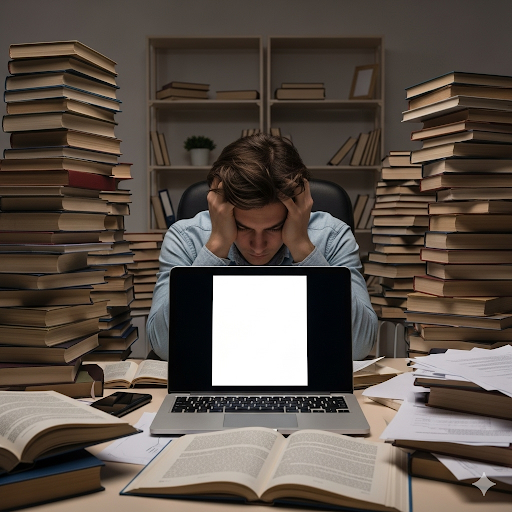
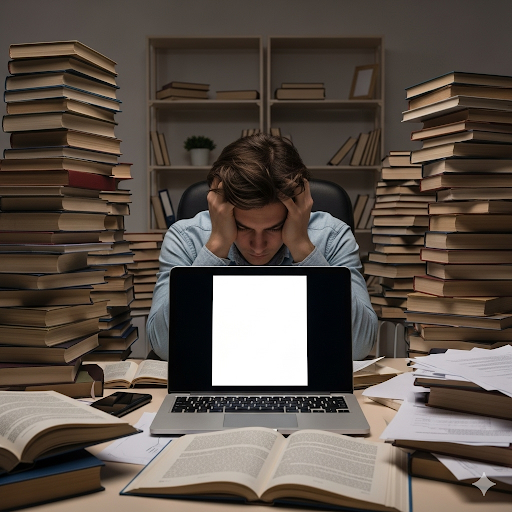
結構勉強したつもりで、論理設計の部分はできてきたと思っていたのに、この結果では、また合格できないのではないかと怖さしかありません。
動画やテキストはたくさん見て、分かった気になっていました。
でも、いざ問題を解こうとすると、手が止まってしまって。
それこそが1つ目の誤りです。「知っている」と「できる」は違います。アウトプットの練習を繰り返さなければ、知識は「使える力」に変わりません。
そうか…。これまでstudyingの動画講座を何回も見て、問題も軽く解いたら、後はパターン分析を必死にやって、解けた問題を解き直してできた気になっていました。完全にインプットに偏った勉強の仕方ってことですね?
以前から、AIと会話をして、私の勉強法がオーディブルを聞きながら、時間だけ消費して満足していたり、内容の理解よりも無駄に時間を使って、わかったつもりになっていたものという指摘を受けていました。
時間をたくさん使ったら、それでいいという無意識の認知もあったのですが、気付きもしないでやってました。
ただ、動画を見るだけ、テキストを読むだけというのがダメなのはわかっていました。
なので、問題を解いた後、解説動画などを見ながら、ノートに問題ごとのパターン分析を実施して、書き出すということを結構やっていました。これで他の問題にも応用できると思い込み、パターンにはまれば解答できると思い込んでいたのでした。
結局、アウトプットしていたつもりがインプットに偏った勉強の仕方の呪縛から解き放たれていなかったということだと思います。
AIからは、以下のことも指摘を受けたので、その点も今後アウトプットの練習の中で、克服していきたいです。
- 時間的プレッシャーへの不慣れ
- 制限時間内に膨大な情報を処理することへの慣れがないと思います。これも時間を測ってのアウトプット練習不足が引き起こしたものなので、慣れるには回数をこなさないといけません。
- 不測の事態への対応力の不足
- 文章の読解でつまずいたときに、どう対処すればいいか、頭の中で次の行動が整理できていない。これもアウトプットしながら確立していけばよかったものができていない結果です。今後の課題の一つです。
致命的な誤り②:合格を遠ざける完璧主義


時間が足りなくなった原因はなんだと思いますか?
模試で時間が足りなかったのは、問題を全部完璧に解こうとして、難しかったり、読み解くのに時間がかかる問題に時間を掛けすぎてしまったためだと思います。
まさにその通りです。それが2つ目の誤りです。合格は60点であり、100点を目指す必要はありません。「取れる問題を確実に取る」という戦略が必要です。
そうか…。難しそうな問題は潔く見切って、解ける問題に集中すればよかったんですね。
これもまったく気づいていませんでした。基本的に試験なので、全問解ききらないといけないという無意識の認知がありました。学生時代は当然かもしれませんが、全部解かないと成績に響く、諦めずに解答用紙は埋めなければいけないというのが当たり前でした。
なので、諦める、見切りを付けるという頭は全くなく、一つの問題にこだわって解き続けるというのが癖になってしまっていたのだということに他なりません。
AIからは以下のような解決案を提示してくれました。
- 完璧主義を手放す
- 制限時間内で「できること」に集中します。論理設計問題は、満点を取る必要はありません。設問1や設問2など、比較的点数が取りやすい前半部分を確実に解く練習から始めましょう。
- 難しい問題や、文章読解に時間がかかりそうな問題は、後回しにしたり、最悪の場合は捨てるという勇気も必要です。
- 「確実に点数を積み重ねる」
- 一つの問題に固執せず、複数の問題から部分点を積み重ねていく方が、点数計算上は有利です。
- 見切り力を鍛える
- 「この問題は時間がかかりそうだな」と瞬時に判断し、次の問題に移る訓練をしてください。これは、本番形式の演習でしか身につかないスキルです。
- 解く順番を変える
- 最初に全設問にざっと目を通し、最も得意な設問から手をつけるという戦略も有効です。得意な問題から解くことで、スムーズに解答が進み、落ち着いて後の問題に取り組めます。
これから、この2つの練習を過去問演習に取り入れて実施していこうと思います。
致命的な誤り③:自分を責める負のスパイラル


模試の結果が悪くて自己嫌悪に陥り、ジムに行く予定をキャンセルしようか迷っています。もっと勉強しないといけない気持ちが大きくて、ジムなんて行ってはいけない気がします。
それが3つ目の誤りです。それは「負のスパイラル」であり、合格を遠ざけます。リフレッシュは、合格のための「自己投資」です。自分を罰するのではなく、未来のパフォーマンスのために、休むことを選択してください。
そうか…。この後のジムは、逃げではなく、合格のための行動なんですね。
今まで、資格試験の勉強をしていて、問題を解いた結果が悪かったり、勉強の進捗が悪いと感じると、いつもその後に予約しているスポーツジムでのプログラムをキャンセルするということを繰り返していました。
これは、私がスポーツジムへ行くことを勉強からの逃げや、サボりだと無意識に感じて、それをキャンセルして自分に罰を与えることで、勉強ができていないことから逃げていたのということに他なりません。
ただ、結果的にジムに行かないと同時に勉強にも手がつかず、結局何もしないままになり、スポーツジムに行っても良かったなとなるのが、いつものパターンでした。
AIからも、「自分はダメな人間だ」「まだ合格ラインに達していない」と感じ、自分を罰するためにリフレッシュを禁止し、ジムに行くことは「罰からの逃避」と無意識的に捉えられ、「まだ頑張りが足りないのに休むなんて許されない」という自己嫌悪が、ジムに行く行動を阻害していると言われました。細かくは以下です。
- オール・オア・ナッシングの思考
- 「今日は完璧に勉強を終わらせるべきだ」という理想があり、それが崩れる(模試の惨敗、イライラ)と、「もう今日はすべてがダメだ」と感じてしまいます。
- 結果、リフレッシュのための行動(ジム)も許せなくなり、「勉強」か「逃避」かの二者択一になってしまいます。
- 自己懲罰としての学習(逃避としてのリフレッシュの禁止)
- 模試の結果が悪いと、「自分はダメな人間だ」「まだ合格ラインに達していない」と感じ、自分を罰するためにリフレッシュを禁止します。
- ジムに行くことは「罰からの逃避」と無意識的に捉えられ、「まだ頑張りが足りないのに休むなんて許されない」という自己嫌悪が、ジムに行く行動を阻害します。
この状況を打破するためにAIから提案されたは、心理的抵抗がある中でスポーツジムに行く、でした。
それが望ましい理由は以下でした。
- 目的の変更
- ジムに行く目的を「リフレッシュ」から「自己嫌悪のサイクルを断ち切るための行動療法」に変えます。
- 認知の書き換え
- 「勉強ができなかったから休む」のではなく、「脳が疲弊しているから、運動で集中力とポジティブな感情を取り戻し、明日の学習効率を最大化する」と認識してください。
- 実行
- 身体を動かし、汗を流すことで、午前中に溜まったネガティブな感情を物理的に外に排出することができます。
このような行動を実行することで、自分の認知を変えて、勉強をより良い方向に持っていけるのでは?と思いました。
ここから1ヶ月、こちらも意識していきます!
まとめ:恐怖から合格へのターニングポイント


あなたとの会話で、3つの誤りに気づきました。この経験は、私にとって大きなターニングポイントになりそうです。
その気づきこそが、あなたの合格への最大の武器です。この学びを活かせば、あなたは必ず合格できます。
最後にAIとこんな会話をしました。
今回の模擬試験は、私にとってただの「失敗」ではありませんでした。それは、合格を阻む3つの致命的な誤りを私に気づかせてくれた、貴重な「ターニングポイント」でした。
私は、AIとの対話を通じて、以下の事実に直面しました。
- 知識は「知っている」だけでは意味がない。
- 完璧主義は、自分を苦しめる呪いだった。
- そして、自分を責めることは、何も生み出さない。
この気づきがなければ、私はおそらく、本番でも同じパニックに陥り、また不合格の現実を突きつけられていたでしょう。
このブログを読んでいるあなたも、もし私と同じように不安を抱えているなら、どうか安心してください。私たちは決して一人ではありません。そして、今この瞬間に、自分の弱点に気づけたことは、最高のチャンスです。
恐怖は、諦める理由ではありません。
恐怖は、行動を変えるための最大のエネルギーです。
私は、この経験を胸に、残りの1ヶ月を全力で走り抜けます。今後はアウトプットと戦略的な学習に集中し、必ず合格を掴み取ります。
そして、このブログを通じて、あなたの合格への道もサポートできたら幸いです。